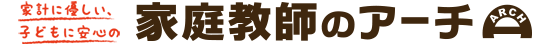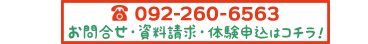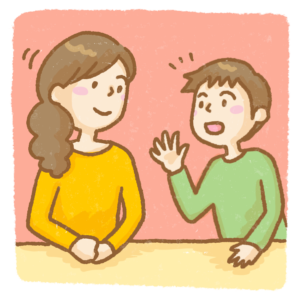不登校の中学生は治る?復帰までのステップと親ができる支援方法を解説【2025年版】
こんにちは!家庭教師のアーチ、代表の白岩です。
今回は「不登校の中学生が治るまで」をテーマにお話ししていこうと思います。

不登校の中学生が治るまで
このページをご覧になっている保護者さまは、中学生のお子さまが不登校になっている状態で、

うちの子の不登校は治るのかしら…
このような不安を抱えながら日々過ごされているのではないでしょうか?
この記事では、不登校の中学生が学校復帰するまでの流れや兆候、そして不登校が治るまでに親ができることなどを分かりやすくまとめています。少しでもご家庭のサポートになれば嬉しいです。
▼もくじ
不登校は病気?
まず、中学生が不登校になることは、一般的に「病気」として捉えられるものではありません。むしろ、思春期特有の心理的・社会的な原因によって引き起こされる現象と考えられています。
不登校とは、学校に行くことに大きな不安や抵抗を感じ、様々な原因で登校を拒否してしまう状態です。具体的には、いじめや学業のプレッシャー、家庭の問題、精神的な不安障害やうつ病などが影響するケースが多くあります。
「不登校は病気」と決めつけるのではなく、背後にある心理的・精神的な背景を理解し、適切なサポートや専門家との連携が必要です。
▼関連記事
不登校を放っておくとどうなる?
不登校状態の中学生を長期間放置してしまうと、以下のようなリスクや問題が発生する可能性があります。
①学業の遅れ
登校しない期間が長引くことで、教科内容に大きな遅れが生じ、進路や将来の選択肢に影響を与える可能性があります。

②社会的スキルの低下
学校は、友達と協力し合いながらコミュニケーションを学ぶ場でもあります。不登校によって対人関係の機会が少なくなると、社会的スキルの習得が難しくなることが考えられます。
③自己肯定感の低下
「自分は学校へ行けない」「みんなと違う」といった思いから、自己否定的な感情を抱きやすくなり、自己肯定感を著しく下げてしまうことがあります。

④精神的な問題の悪化
不登校の原因として不安やうつなどの精神的な問題がある場合、適切な対応をしないまま放置すると、症状がさらに悪化する可能性があります。
⑤人間関係の悪化
保護者もお子さまの状況にストレスを感じるあまり、家庭内で衝突が起きやすくなります。また、友人との距離も広がり、孤立を深めることにつながります。

不登校を放っておくと、こうしたさまざまな弊害が出てくるため、早期のアプローチや適切なサポートが重要です。学校や家庭、専門家が連携しながら、子どもの状況を把握し、対策を立てましょう。
学校復帰までのステップと必要な対応
不登校の中学生が治るまでの道のりは、原因や性格、家庭環境などによって異なりますが、大まかにいくつかのステップに分けられます。以下に一般的な流れと必要な対応を示します。
①早期対応期(不登校が始まった直後)
- 不登校の原因をできるだけ早く把握し、学校や専門家と連携する
- 子どもの心理状態を理解し、カウンセリングなどのサポートを検討
- 親子でしっかりと話し合い、焦らず状況を整理する

②中期対応期(不登校が数週間から数ヶ月)
- 定期的なカウンセリングや家庭学習の導入など、継続的なサポートを実施
- 学校側と復帰計画について相談し、連携を深める
- 自己肯定感を高める活動や、少人数での学習支援を検討
③復帰準備期(学校復帰への取り組みが始まる時期)
- 校内見学や一部授業への参加など、段階的に学校へ慣れる工夫
- 子どもの気持ちを尊重しつつ、ペースを見ながら復帰を促す
- 個別指導や学習塾を利用して、遅れてしまった学業を補う
アーチの不登校サポートとは?

④学校復帰期(学校生活に徐々に復帰する時期)
- 学校や家庭、専門家が連携してこまめに子どもの状態をチェック
- 友人関係や学業のリカバリーに対して継続的なサポートを行う
- 子どもの不安や疲れを最小限に抑え、必要に応じてスケジュールを調整
⑤完全復帰期(学校生活が安定していく時期)
- 学校生活に適応しはじめ、不登校の状態から回復した段階
- 引き続き必要に応じてカウンセリングやサポートを継続
- 子どもが自己肯定感を保ち、学校行事や部活動などへも参加できるようになる

これらのステップはあくまで一例であり、個々のケースによって異なります。大切なのは、焦らず子どものペースに合わせながら、学校・家庭・専門家が一丸となって対応していくことです。
復帰準備期に見える兆候
不登校の中学生が治る前段階として、「復帰準備期」に入っていることがうかがえるサインは以下のとおりです。
- 学校に対する興味や関心が戻り、学校や友人の話題に前向きになる
- 「学校に行ってみたい」といった意欲の増加
- 学校に対する不安や恐怖が少しずつ改善される
- 少しずつ自己肯定感が高まり、自信を取り戻す
- 感情コントロールやストレス対処がうまくなり、落ち着きを見せる
- 社会的スキル(友達とのコミュニケーションなど)が回復傾向にある
このような兆候が見られたら、学校復帰に向けて段階を踏んだ計画を立てると同時に、無理をさせず、子どもの心に寄り添った声かけをしてあげましょう。

学校復帰までに時間がかかる理由
不登校が治るまでの期間は人それぞれで、数週間で復帰できる場合もあれば、半年以上かかることもあります。その理由として、以下の要因が考えられます。
- 原因が多様で、それぞれに合った対応が必要
- 心に負った傷の回復に時間がかかる
- 学校に対する不安や恐怖心が強く、慎重なサポートが求められる
- 学業や社会的スキルの遅れを取り戻すための段階的な学習が必要
- 子どもごとに異なるペースで回復していく
- 学校や家庭、専門家などの連携不足で支援が行き届かない場合もある
不登校が治るまでの効果的な取り組み
- 専門家によるカウンセリングや心理療法
- 学校との連携を密にし、こまめな情報共有を行う
- 個別指導や少人数クラスで学業サポートを受ける
- 段階的に学校へ顔を出し、学校復帰の負担を軽減
- 回復後も継続してフォローアップし、再不登校を防ぐ

不登校を克服するために親が出来ること
不登校を克服するためには、親の役割もとても大切です。以下のポイントを参考にしてみてください。
- 子どもの気持ちを理解する
・「なぜ行けないのか」「何を不安に感じているのか」を一緒に考える - 安定した家庭環境を提供する
・家庭内のトラブルやストレスを減らし、子どもが安心できる環境を整える - 学校との連携
・子どもの状況を担任やカウンセラーと密に共有し、サポート体制を整える - 専門家との協力
・心理カウンセラーや精神科医などの意見を取り入れ、必要に応じて治療やサポートを受ける - 子どものペースに合わせる
・無理に学校へ行かせようとせず、段階を踏んで復帰を目指す - 学業や社会的スキルのサポート
・家庭教師やオンライン学習を活用し、遅れやすい教科を補う
・友人との交流やコミュニケーションの場を用意する - 継続的なフォローアップ
・学校復帰後も定期的に状態をチェックし、必要があればいつでも相談できる体制を整える

▼関連記事 アーチのオンライン家庭教師とは?

起立性調節障害(OD)とは?
不登校の中学生に多い原因のひとつとして「起立性調節障害(OD)」があります。家庭教師のアーチでも、この症状によって朝起きられず、不登校状態となっている中学生を多く担当しています。
定義と概要
起立性調節障害とは、立ち上がる際に血圧や心拍数がうまく調整できず、めまいや立ちくらみが起こる疾患です。朝起きられないなどの症状が特徴的で、中学生の不登校や学業不振につながることがあります。
中学生に多い理由
- 思春期の急激な成長により、自律神経のバランスが乱れやすい
- 夜更かしや生活リズムの乱れ、学校生活のストレスなど
発症率
中学生の10〜20%がこの症状を経験すると言われており、特に女性に多い傾向があります。
主な症状
- 朝起きられない
- めまい、立ちくらみ
- だるさや頭痛、集中力の低下
- 学業への支障や部活動への参加が困難になる
診断方法
- 10分間起立試験や医師の問診
- 小児科や内科を受診し、血圧や心拍数の変化を測定
中学生の生活への影響
- 遅刻や欠席が増え、学業が遅れやすい
- 家族から「怠けているのでは」と誤解され、親子関係がギクシャクするケースも
起立性調節障害の治療と対策
医療的なアプローチ
- 薬物治療
血圧を安定させるための薬や自律神経を調整する薬が使用されます。 - 心理的サポート
不安やストレスを軽減するため、カウンセリングが有効です。
生活習慣の改善
- 睡眠リズムの確保
毎日同じ時間に就寝・起床する習慣をつけましょう。 - 水分と塩分の摂取
こまめな水分補給と適度な塩分摂取が自律神経を整えます。 - 朝の起床方法
ベッドで数分間ゆっくり座るなど、急な立ち上がりを避ける工夫が大切です。
学校との連携
- 診断書の提出
学校に理解を求め、登校時間の柔軟性や課題の配慮を依頼します。 - オンライン学習の活用
不登校が続く場合、オンライン授業を取り入れることで学業を継続できます。
親ができるサポート
- 子どもの気持ちを受け止める
「怠けている」と決めつけず、体調に寄り添う姿勢が大切です。 - 無理をさせない
完全に回復するまでは、学校への強制的な登校を避けましょう。

実際の体験談
体験談1:周囲の理解が得られたことで前向きに

男子
最初は『ただの朝寝坊』と先生や友達に誤解されて辛かったです。でも、診断を受けて学校に説明したところ、登校時間を少し遅らせてもらえるようになりました。体調に合わせた登校を続ける中で、友達も『無理しなくていいよ』とサポートしてくれるようになり、学校が楽しくなりました。
体験談2:水分補給の工夫で改善

女子
朝、立ちくらみやだるさで動けなかったのですが、医師に『起きたらすぐ水を飲むように』と言われて試してみました。それだけで、少しずつ朝の動きが楽になりました。今は寝る前に枕元に水を用意し、朝飲むのが習慣です。
体験談3:オンライン学習の活用

女子
朝が特に辛く、長い間学校に行けませんでした。でも、学校がオンライン授業を用意してくれたおかげで、家でも無理なく勉強を続けられました。今は体調が安定してきたので、週に2〜3日は登校できるようになり、自信がつきました。
体験談4:家族の協力で乗り越えた

男子
親が最初は『甘えてる』と言っていましたが、病院で診断を受けた後は、生活リズムを整えるために一緒に努力してくれました。例えば、夜はスマホを置いて早く寝るように声をかけてくれたり、朝もゆっくり起こしてくれたり。家族の支えがあったおかげで少しずつ学校生活が戻ってきました。
体験談5:部活との両立が可能に

男子
陸上部に所属していましたが、起立性調節障害の影響で朝の練習や大会に参加できない日が増えました。医師の指導で水分や塩分をしっかり摂り、朝練は無理せず夕方の練習だけ参加する形に変更しました。顧問の先生も理解してくれて、無理せず活動を続けられるようになりました。大好きな部活をやめずに済んで本当に良かったです。
起立性調節障害(OD)まとめ
適切なサポートと治療を受ければ、起立性調節障害は十分に回復が期待できる症状です。大切なのは、学校や家族が理解を示し、子どもの体調に合わせた柔軟な対応をすること。そうすることで、中学生は再び充実した学校生活を取り戻すことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
- 中学生が不登校になることは、単に「病気」というよりは心理的・社会的要因が大きい
- 不登校をそのまま放置すると、学業や人間関係、自己肯定感などに悪影響が及ぶ可能性が高い
- 不登校が治るまでには、原因や子どもの性格、家庭環境によって異なる段階がある
- 早期発見・早期対応が回復と克服の鍵となる
私たち家庭教師のアーチでは、多くの不登校の中学生をサポートしてきました。オンライン指導にも対応していますので、
- 指導曜日や時間
- 指導教科や学習レベル
- 不登校特有の悩み(学習の遅れや社会的スキルの低下など)
といったご要望に合わせ、柔軟に講師をご紹介しております。実際にご利用いただいたご家庭からも、「子どもが自信を取り戻した」「不登校が治るきっかけとなった」といった嬉しいお声を頂いております。
少しでも気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。保護者さまと一緒に、お子さまの学校復帰や将来を見据えたサポートを行ってまいります。
一日でも早く、お子さまが笑顔で学校に通えるようお祈りしております。