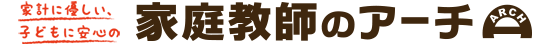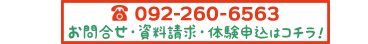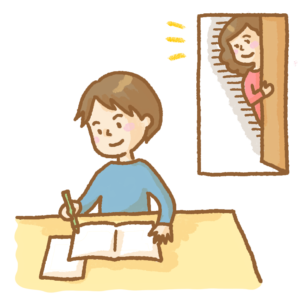【2025年版】不登校の中学生が通える施設まとめ|支援内容・費用・成功事例も解説
中学生のわが子が不登校に…。
「このままで将来は大丈夫?」「どこに相談すればいいの?」と、不安でいっぱいの方へ。
この記事では、支援施設の種類・費用・選び方・体験談まで、不登校の中学生と向き合うために必要な情報をわかりやすく解説します。

▼もくじ
1. 不登校の中学生に「施設」という選択肢が必要な理由
中学生の時期に不登校になると、保護者としては「将来は大丈夫だろうか」「このまま放っておいていいのか」といった不安が尽きません。
特に思春期に入った中学生は、家庭内でのコミュニケーションが難しくなりがちで、親子関係もギクシャクしてしまうことが多いものです。
不登校が長引くと、生活リズムの乱れや人との関わりの減少が重なり、子どもが自己否定感を強めてしまうことがあります。こうした状態が続くと、いわゆる「引きこもり傾向」に発展することも少なくありません。
こうした時期に重要なのが、学校とは別の「もう一つの居場所」です。
家庭では対応が難しい部分を第三者がサポートすることで、子ども自身が少しずつ前向きな気持ちを取り戻していくことができます。
施設に通うことで得られるのは、学習支援だけではありません。
安心できる大人との関係や、同じような立場の仲間との交流、そして「無理せず通える場所がある」という安心感が、子どもの自己効力感を育み、将来的な社会復帰や高校進学への土台となっていきます。

2. 不登校の中学生が通える支援施設の種類と特徴【5タイプを紹介】
不登校の中学生を支援する施設には、目的や支援内容の異なるさまざまな種類があります。
ここでは代表的な5つの支援施設について、その特徴と違いをご紹介します。
① フリースクール|自由な学びと人間関係の再構築
フリースクールは、学校に行けない子どもが「自分らしく過ごせる居場所」として全国に広がっています。
学年の枠にとらわれず、子どものペースに合わせた家庭学習型の指導や、創作・体験活動などを通して、社会性の回復も図られます。
通学型・オンライン型のどちらにも対応している施設も増えており、自宅から参加できるのも大きなメリットです。
また、学校と連携して出席日数として認められることもあるため、「高校進学を見据えて通いたい」というニーズにも応えやすくなっています。
▼小学生向けフリースクールの情報も知りたい方はこちら
② 教育支援センター(適応指導教室)|学校復帰を目指す公的支援
教育支援センターは、教育委員会が設置・運営する公的な不登校支援施設です。
適応指導教室とも呼ばれ、在籍校と連携しながら学校復帰を目指す取り組みを行います。
個別・少人数制の学習支援に加えて、心理士による面談やカウンセリング、保護者支援なども用意されている場合が多く、心理支援にも重点が置かれています。
費用は原則無料で、安心して利用できる点も魅力です。
③ 通信制高校・サポート校との連携支援|中学生からの進路準備
最近では、中学生の段階から通信制高校やサポート校とつながる事例も増えています。
たとえば、「中学生向けのオープンスクール」や「体験入学プログラム」などがそれにあたります。
「学校に戻るのは難しいけれど、高校には進学したい」という子どもには、こうした場が学び直しや進学支援の第一歩になります。
学習面・心理面の両面を支えるスタイルが多く、保護者からの評価も高い選択肢です。
▼不登校からの高校進学について詳しく知りたい方はこちら
【2025年版】出席ゼロでも高校進学できる?中学生の不登校×受験成功のポイントを徹底解説!
④ 自立支援施設・寮付き施設|家庭だけでは対応が難しいときの選択肢
家での対応に限界を感じているご家庭や、長期的に引きこもり傾向が強いお子さんには、「自立支援施設」や「寮付きの不登校支援施設」が選ばれることもあります。
どんな特徴がある?
- 寮生活を通じて生活リズムを整える
- 学習支援・社会性の回復プログラムあり
- 食事・生活支援・カウンセリングなど一体型
費用は民間運営のためやや高額ですが、精神的なリセットや環境のリフレッシュを目的に数ヶ月~1年単位で預けるケースもあります。
⑤ カウンセリング施設やメンタルクリニック|心のケアが中心
学校に行けない背景には、不安障害・うつ・発達特性など心の問題が関係していることも少なくありません。
その場合、医療機関と連携した心理支援施設や、児童思春期に特化したカウンセリングセンターの利用が検討されます。
こんな支援があります
- 臨床心理士や精神科医によるカウンセリング
- 発達検査や知能検査によるアセスメント
- 医療的ケアと教育支援の併用
「学校に行かせる」ことが目的ではなく、まずは心の安定を図るというスタンスが基本です。

3. 【比較表つき】支援施設の費用目安と使える助成制度
施設選びを考えるうえで、「費用面の不安」は避けて通れません。
ここでは、主な施設ごとの費用相場と、活用できる公的支援制度について紹介します。
施設別|費用相場の目安
| 施設タイプ | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| フリースクール | 月額1〜5万円 | 地域やプログラムにより幅あり。助成制度ありの自治体も。 |
| 自立支援施設(寮付き) | 月額10〜20万円前後 | 生活支援・学習・心理支援がセット。民間運営が多く高額傾向。 |
| カウンセリング施設 | 1回5,000〜10,000円 | 臨床心理士や精神科医による対応。医療保険が適用されるケースも。 |
| 家庭教師(在宅型支援) | 1時間1,800〜3,000円 | 学習遅れのリカバーに柔軟対応。オンライン対応もあり。 |
▼家庭教師サービスの料金相場を比較したい方はこちら
利用できる助成制度(例)
- 就学援助制度:学用品・給食費・交通費の一部補助(市区町村単位)
- ひとり親家庭支援:学習支援・奨学金・医療費助成など
- 生活保護世帯向け:学習支援事業の提供や学費の公費負担
- NPO・地域団体の無料支援:学習ボランティア、夜間教室などの選択肢も
こうした制度を活用することで、家庭の経済的な負担を軽減しながら支援を受けることが可能です。
4. 施設選びで失敗しないための5つのチェックポイント
不登校中学生を受け入れる支援施設は、全国に数多くあります。
しかし「何となく良さそう」で選んでしまうと、お子さんに合わず、結果的に続かないこともあります。
ここでは、施設選びで後悔しないためのチェックポイントを5つ紹介します。

①子どもの性格・特性に合っているか?
- 人付き合いが苦手 → 少人数制のフリースクールや在宅型支援
- 活動的で外出が好き → フィールド活動が多い施設
- 発達特性がある → 発達障害の理解が深い支援者がいるか確認
特にADHDやASDなどの発達特性がある場合、専門のカウンセラーや心理士が在籍している施設がおすすめです。
②学習支援の体制は十分か?
長期の不登校で学習遅れがある場合、高校進学に向けたサポート体制は必須です。
苦手科目を一つずつ克服したいならマンツーマン指導が有効。家庭教師や個別対応型のフリースクールなども検討しましょう。
③心理支援・カウンセリング体制の有無
学習よりもまず「心の安定」が必要なお子さんには、心理支援の充実度が重要です。
心理士の常駐、定期的な面談、親子カウンセリングがあるかどうかを確認してください。
④通いやすさと続けやすさ
- 通学時間が1時間以上かかる → 負担が大きく継続しづらい
- 週何日通う必要があるのか
- オンライン対応の有無
地方在住の場合は、Zoomなどを活用したオンライン家庭教師や、遠隔対応のフリースクールとの併用も現実的な選択肢です。
⑤在籍校や高校との連携があるか
施設と学校が連携している場合、在籍校での出席扱いになるケースがあります(学校長の判断による)。
また、施設によっては高校進学サポートまで一貫して行ってくれるところもあります。
5. 実際に施設を利用した親子の体験談【成功のきっかけ】
ここでは実際に施設を利用したご家庭の声をご紹介します。
リアルな体験談は、今まさに迷っている保護者にとって大きなヒントになります。
フリースクールで笑顔を取り戻したAくん

中学2年の夏から完全不登校になったAくん。
朝になると頭痛や腹痛を訴え、部屋から一歩も出なくなった日が続いたそうです。
そんなとき、お母さんが見つけたのが地域のフリースクール。
まずはZoomによるオンライン体験から始め、スタッフとの個別面談を経て、3ヶ月後には「行ってみようかな」と話すようになりました。
現在では週3回通いながら、ものづくりや音楽活動を通して少しずつ笑顔を取り戻し、「高校に行くのもいいかも」と話すようになっています。
寮付き支援施設で大きく変化したBさん

中学に入ってから不登校が続き、夜型生活とゲーム依存が強まったBさん。
家庭内の会話もなくなり、暴言・無視・引きこもりが日常になってしまいました。
限界を感じたお父さんが選んだのが、寮付き自立支援施設。
1年間の寮生活のなかで、生活リズムや他者との関わり方を身につけ、半年後には「高校に行ってみたい」と自分から話し始めたそうです。
6. よくある不安・疑問Q&A【施設を検討する前に知っておきたい】
「施設を使うのが初めてで不安…」という保護者の方へ。実際によくある疑問を、Q&A形式でわかりやすくまとめました。

Q. 子どもが施設に行きたがらない時はどうしたらいいですか?

A. 無理に通わせるのは逆効果です。
まずは保護者がパンフレットや動画で情報を集めて、子どもと一緒に見ることから始めましょう。
オンライン面談など、低ハードルな接点を活用するのが効果的です。

Q. 不登校だと高校進学に不利になりますか?

A. 不登校経験が直接的な不利になることはありません。
むしろ最近では、面接重視型入試や自己推薦型入試など、不登校生を歓迎する制度が増えています。
フリースクールや家庭教師でも進学支援は可能です。
▼中学生の不登校と高校受験の最新事情はこちら

Q. 寮付きの施設に預けるのが不安です…

A. 見学・面談は必須です。
施設スタッフの対応方針や生活環境を確認し、月1回の面会・定期報告制度があるかどうかも重要なチェックポイントです。

Q. 学校との関係はどうなりますか?

A. フリースクールや教育支援センターは在籍校と連携しているケースが多く、出席扱いとなる可能性もあります(学校長判断)。
また、進路変更時の在籍校手続きもあるため、早めに相談を始めるのが安心です。
7. 迷ったらまずこれ!行動ステップ3選【情報収集〜相談まで】
「施設を使った方がいいのかも」と思っても、最初の一歩が踏み出せない…。
そんなときは、焦らず小さな行動から始めるのがコツです。
① まずは親が冷静に情報を集める
不登校に向き合うとき、保護者の不安や焦りは子どもにも強く伝わります。
まずは冷静になるためにも、施設の種類・支援内容・費用などを把握し、比較検討できる材料を揃えましょう。
- 施設の公式サイトを確認
- 学習支援や心理支援の特徴を比較
- 公的制度や助成金の条件を調べる
情報が整理できると、判断にも自信が持てるようになります。
② 子どもと話すタイミングを見極める
親が「動かなきゃ」と思っても、子どもにとってはタイミングが合わないこともあります。
いきなり「施設に行こう」と言うのではなく、まずは動画やパンフレットなどを一緒に見たり、体験談を共有するだけでもOKです。
“選べる”感覚を大切にすることで、子どもが自分から動き出せる環境が整います。
③ 第三者の相談窓口を活用する
学校の先生やスクールカウンセラーだけでなく、フリースクール、支援NPO、家庭教師サービスなども含めて、第三者に相談することが第一歩になります。
「このまま家庭だけで抱えていて大丈夫だろうか…」
そう感じた時こそが、誰かと一緒に考えるタイミングです。

8. 「家庭教師のアーチ」でも不登校中学生を支援しています
私たち「家庭教師のアーチ」では、不登校中学生の学習・生活支援を全国対応で行っています。
「学校に通うのはまだ難しいけれど、勉強をやり直したい」「外出せずに誰かと関わりたい」——そんなお子さんの声に応えるサービスです。
家庭教師のアーチの特徴
- 訪問型・オンライン型どちらにも対応
- 不登校支援に理解ある講師が多数在籍
- 学習サポートだけでなく、話を聞いてもらえる安心感を大切に
- 高校進学・定期テスト対策もOK
- 明瞭な料金設定(訪問:1,800~2,000円/オンライン:1,500~1,800円)
▼アーチの詳しい料金はこちら

こんなお子さんに向いています
- 学校に行けず、学習遅れが気になる
- 集団が苦手で、家庭学習を自分のペースで進めたい
- フリースクールとの併用で、さらに個別の勉強支援を受けたい
- 高校進学のために準備を始めたい
「まずは相談だけしたい」「子どもが拒否するかもしれないけど…」そんな方も大丈夫です。
無料体験レッスン・資料請求は、公式サイトよりいつでも受付中です。
▼「家庭教師のアーチ」の
無料体験レッスンはこちら

9. まとめ|お子さんに合う“もう一つの居場所”は、必ず見つかります
不登校の中学生を支えるための施設や支援の選択肢は、想像以上に多様です。
- フリースクールで自分のペースを取り戻す
- 教育支援センターで学校復帰を目指す
- 寮付き支援施設で生活を立て直す
- 家庭教師や在宅支援で学び直す
- 医療機関やカウンセリングで心をケアする
どれが正解かは、お子さんの状況とご家庭の考え方によって異なります。
大切なのは、「学校に行けない=終わり」ではなく、「今の状態に合った新しい居場所」を見つけることです。
あなたの子どもにとって、本当に安心できる場所はきっとあります。
焦らず、ひとつずつ、できることから始めていきましょう。