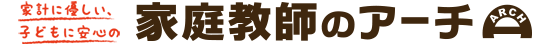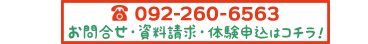不登校の原因ランキング【小学生・中学生別】親が知るべき対応策も解説|2025年最新版
「うちの子、最近学校に行きたがらない…」
「理由を聞いても『行きたくない』しか言わない…」
そんな悩みを抱える保護者の方が、年々増えています。
たとえば、
- 朝になるとお腹が痛いと言う日が増えた
- 学校から帰ると無言。何かあったのか聞いても話さない
- 勉強の話になると涙ぐむ
不登校になる理由は一つではありません。 いじめ、学習の遅れ、家庭の事情、心の問題など、複雑な要因が絡み合っています。
この記事では、不登校の主な原因をランキング形式で紹介しながら、親として何ができるのか、小学生・中学生の傾向に分けて解説します。 さらに、家庭学習や心のケアを支える手段として注目されている「家庭教師」の活用についてもご紹介していきます。

▼もくじ
1. 不登校の主な原因ランキング【2025年版】
1位:いじめ・人間関係のトラブル

不登校の最大の理由は、やはり「いじめ」や「友達との関係」などの人間関係の悩みです。
- クラスでの孤立
- SNSでの悪口や無視
- 仲良しグループに入れない
こうしたことが続くと、子どもは学校に強いストレスや恐怖を感じるようになります。
特に中学生は思春期特有の敏感さもあり、少しのきっかけで深刻な悩みにつながることも。
親ができる対応策
- 「学校に行きなさい」と無理強いしない
- 「何があったの?」と否定せずに話を聴く
- 学校と連携しつつ、本人の安全と安心を第一に考える
「今日はお休みしようか?」と声をかけるだけで、子どもが少し安心することもあります。
2位:学習の遅れや成績不振

「授業についていけない」「テストが悪いと怒られる」—— そうしたプレッシャーから不登校になるケースも多く見られます。
特に中学に入ると勉強が一気に難しくなり、小学生の頃の苦手が表面化しやすくなります。
また、発達障害(学習障害やADHDなど)を背景に持つ子も、集団授業での学習についていけず、自己肯定感を失いやすくなります。
親ができる対応策
- 怒らずに「何がわからないのか」を一緒に整理する
- 家庭学習のハードルを下げる(短時間・得意科目から)
- 家庭教師など、個別対応の学習支援を検討する
家庭教師は、子どもの理解度に合わせて進められるので、「勉強=つらい」から「ちょっとやってみようかな」へ気持ちを切り替えるきっかけにもなります。
3位:精神的・心理的な問題

- 「朝になるとお腹が痛くなる」
- 「夜眠れない」「気分が落ち込む」
こうしたサインが続く場合、心の不調が関係している可能性も。
中には、うつ症状や不安障害、ASDなどの発達特性が影響しているケースもあります。
親ができる対応策
- 子どもの状態をよく観察する(無理に理由を聞かない)
- 必要に応じて、スクールカウンセラーや専門医の受診も検討
- 学校外での安心できる居場所を探す(家庭教師・フリースクールなど)
「学校に行く/行かない」ではなく、「安心して過ごせる時間を少しずつ増やす」ことを第一に考えると、子どもの表情が変わってきます。
4位:家庭環境の問題

家庭での不安定な状況やストレスも、不登校の大きな要因になります。
たとえば、
- 両親の不仲や離婚
- 経済的な不安や生活の乱れ
- 親の過干渉、逆に無関心な態度
こうした環境が続くと、子どもは「家でも安心できない」「誰にも話せない」と感じ、心の居場所を失ってしまいます。
親ができる対応策
- 家庭の中で安心できる時間・会話を増やす
- 子どもに八つ当たりせず、まず大人が心の余裕を持つ
- 必要に応じて福祉サービスや専門機関に相談する
また、第三者として家庭教師を入れることで、家庭内に“安心できる他人”の存在ができるという効果もあります。
5位:学校の雰囲気や教育方針が合わない

「先生が厳しすぎる」「自由がなさすぎて息苦しい」
そんな声も、不登校につながる大きなきっかけです。
特に、
- 一律の指導に馴染めない子
- 個性を認めてもらえないと感じる子
- 高圧的な教師に恐怖心を抱く子
などは、「この学校は自分には合わない」と感じ、足が遠のいてしまうことがあります。
親ができる対応策
- 学校とじっくり話し合い、柔軟な対応を相談する
- 転校やフリースクール、家庭学習などの選択肢を知る
- 家庭教師のような個別対応で子どもの安心を確保する
学校に適応することだけが正解ではありません。大切なのは、お子さんが「自分らしく過ごせる環境」を見つけることです。
▼男女で不登校の傾向は異なることも。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2025年版】不登校の中学生|男子・女子それぞれの特徴・原因・親ができる支援と回復へのポイント
2.【年齢別】小学生と中学生で異なる「不登校のきっかけ」
◉ 小学生に多い特徴と親の関わり方
小学生の不登校は、「朝になると泣いてしまう」「お腹が痛くなる」「玄関から出られない」といった“身体の反応”として現れることが多いです。
原因としては、
- 初めての集団生活にうまくなじめない
- 担任の先生との相性
- ささいな失敗や友達関係のもつれ などが挙げられます。
親ができる対応策
- 子どもの話をじっくり聞き、否定せず受け止める
- 「行けた日」を大きく褒める
- 学校と連携して、登校しやすい方法(別室登校、保健室登校など)を相談する
無理に登校させるよりも、「今日は家で安心して過ごしていいよ」と伝えることで、信頼関係が深まり、次のステップにつながることもあります。

◉ 中学生に多い特徴と接し方のコツ
中学生の不登校は、「無気力」「昼夜逆転」「言葉にしない拒否」といった、より複雑なかたちで現れることが多いです。
思春期ならではの葛藤や、進路への不安、友人関係のトラブルなどが重なり、親にも本音を話せなくなる子もいます。
親ができる対応策
- プライドを尊重しつつ、見守る姿勢を大切にする
- 学校以外の相談先(スクールカウンセラー、支援機関)を活用する
- 学習面の遅れを不安にさせないよう、家庭教師などでサポート体制を整える
中学生は「自分で決めたい」「でも助けてほしい」と揺れる時期です。親は“押しすぎず、放置しすぎず”の距離感を意識しましょう。

3. 高校生の不登校傾向と親のサポート法
不登校は中学生までの問題と思われがちですが、高校生でも一定数存在しています。
高校生の不登校で多いのは、
- 勉強・進路に対するプレッシャー
- 自己肯定感の低下
- 親や教師との関係悪化
- SNSでの人間関係疲れ
高校は自主性が重視される一方で、「誰にも頼れない」「もう逃げ場がない」と感じやすい環境でもあります。
親ができる対応策
- 成績よりも「生活が安定しているか」を重視する
- カウンセリングや第三者との接点(家庭教師・支援団体など)をつくる
- 「高校を辞める/辞めない」を焦らず一緒に考える
進学・就職など人生の選択が絡む時期だからこそ、「学ぶこと=未来を閉ざすことではない」と感じられる環境づくりが大切です。

4. 不登校からの進学・高校受験はどうなる?
不登校の状態が続くと、保護者の方からよく聞かれるのが「このままでは高校に進学できないのでは?」という不安です。しかし、実際には不登校のままでも高校進学を実現している子どもは多くいます。
ここでは進路に関するリアルな情報を解説します。
◉ 出席日数が足りないと、高校に行けない?
中学校では「出席日数が足りないと内申点が悪くなる」と言われることがあります。しかし、実際には以下のような柔軟な対応が可能です。
- 学校長の判断で「やむを得ない事情」として配慮される
- 出席以外の活動(家庭学習・支援機関・家庭教師など)が加味される場合もある
- 一部の高校では、内申点よりも「作文」「面接」「自己PR」重視の入試が導入されている

◉ 不登校でも受験できる高校の種類
不登校経験があっても進学できる高校は多数あります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 全日制高校(公立・私立) | 面接や作文中心の学校も。配慮のある学校を選べば不登校経験も不利になりにくい |
| 定時制高校 | 夕方〜夜間の授業。少人数で、働きながら通う生徒も多い |
| 通信制高校 | 登校は月数回または不要。自分のペースで学習でき、在宅中心でも高校卒業が可能 |
子どもに合った進学スタイルを選ぶことで、無理なく未来へのステップを踏み出すことができます。
▼高校受験に関する不安が大きい方はこちらも参考にしてください。
【2025年版】出席ゼロでも高校進学できる?中学生の不登校×受験成功のポイントを徹底解説!
◉ 家庭での学習継続が“進学のカギ”に
受験を見据えるなら、「学校に行けない間、家でどう過ごすか」が重要です。
- 毎日少しずつ勉強の習慣を取り戻す
- 家庭教師や個別塾などで、受験への備えを進める
- 高校側に「努力の跡」を伝えられるような記録を残す(学習記録、読書記録など)
家庭教師を活用して、「安心できる環境で学ぶ→受験準備も自然に進む」という流れがつくれると、不登校の状態からでも前向きな進学が実現できます。

このように、不登校でも高校進学は十分に可能です。「学校に行っていない=将来が閉ざされる」わけではありません。今できることから少しずつ整えていけば、子どもはまた次の一歩を踏み出せるようになります。
5. チェックリスト:もしかして不登校のサインかも?
以下のような様子が続いている場合、不登校の初期サインの可能性があります。
- 朝になると体調不良を訴える(腹痛、頭痛など)
- 日中は元気だが、学校の話になると無口になる
- 宿題や勉強に極端な拒否反応を示す
- 寝つきが悪くなる、昼夜逆転傾向
- 学校行事の前に強いストレスを感じている様子がある
これらがすべて当てはまる必要はありませんが、いくつか重なる場合は、無理に登校を促すよりも「一度立ち止まる」ことが大切です。
家庭教師やフリースクールなど、“学校とは違う選択肢”を知っておくことで、親子ともに安心できる土台ができます。

6. 家庭でできる!子どもの不登校対策5選
不登校の解決に“特効薬”はありませんが、家庭でできる支援はたくさんあります。
1. 無理に登校させない
子どもが「行きたくない」と言ったときは、まず理由を探る前に気持ちを受け止めましょう。「甘えている」ではなく、「助けを求めている」のかもしれません。
2. 話を聴く『傾聴』の姿勢を大切に
アドバイスや指示よりも、「うん」「そうなんだ」と受け止める聞き方を心がけましょう。「この人なら話せる」と思える存在がいるだけで、子どもの不安は軽減されます。
3. 学校以外の学び場を知る
フリースクール、適応指導教室、自宅学習など、学校に代わる学びの場を選ぶことで「学ぶ」ことへの不安や抵抗をやわらげられます。
4. 心のケアを優先する
気持ちのケアをせずに学習ばかりに意識を向けると、逆効果になることも。本人の心の回復を第一に考えることが、結果的に前向きな一歩につながります。
5. 家庭教師という選択肢を検討する
家庭教師は、学校に行けない期間も自宅で学習を進められる有効な支援手段です。ペースに合わせた柔軟な学びで、「わかる」「できる」という感覚を育てます。

7. 支援の選択肢を広げよう|家庭教師以外の支援機関まとめ
不登校への対応には「家庭教師」以外にも、さまざまな支援方法があります。子どもの性格や状況に応じて選ぶことで、より安心できる学びや居場所が得られる場合もあります。ここでは代表的な支援機関をご紹介します。
◉ 教育支援センター(適応指導教室)
各自治体が運営しており、学校に通えない子どもに対して「別の場所」で学ぶ場や社会性を育む支援を行っています。学校と連携しているため、出席扱いとなる場合もあります。
- 対象:小学生・中学生
- 内容:学習支援、体験活動、相談対応など
- 利点:費用負担が少なく、公的な信頼性が高い
◉ フリースクール
「自分のペースで学べる」ことを大切にした民間の学び場。登校の有無にこだわらず、子どもの意欲を大切にした自由なカリキュラムを提供しています。
- 対象:年齢問わず(多くは小中学生)
- 内容:教科学習、創作活動、体験学習など
- 利点:個性や発達特性に応じた柔軟な対応が可能
※文科省の通知により、フリースクールへの通学も「出席扱い」とされる場合があります(学校長判断による)

◉ 心理カウンセリング(公的・民間)
子どもや家庭全体の「心の負担」に寄り添う支援です。学校のスクールカウンセラー、公的相談所、または専門の心理士が在籍するカウンセリングルームなどがあります。
- 利点:子どもが言葉にしづらい感情を少しずつ整理できる
- 保護者自身の悩みも相談できる

◉ 通信制高校(中学生の保護者向け)
不登校が長期化した場合でも、高校進学の道は閉ざされていません。通信制高校は、自宅学習を中心にしながら、月数回の通学やオンラインで学習を進めることができる柔軟な選択肢です。
- 自分のペースで学習が可能
- 不登校経験者も多く、居心地の良さを感じやすい
- 高卒資格を取得しながら、進学や就職も視野に入れられる
▼不登校受け入れ高校の詳細はコチラ
【不登校でも安心】受け入れ高校おすすめ校一覧|通信制・サポート校の選び方も解説
このように、家庭教師以外にも支援の選択肢は豊富にあります。「合う・合わない」は子どもによって異なるため、いくつかの方法を知り、試してみることで「自分に合った道」が見えてくるはずです。
そのうえで、「家にいながら学べて、安心して関われる大人がいる」家庭教師という選択肢も、心強い支えになるでしょう。
8. 家庭教師ができるサポートとは?【不登校支援の実例つき】
◉ 家庭教師の3つのメリット
- 個別に寄り添う柔軟な指導 子どもの理解度や集中力に合わせて、内容もスピードも調整できるため、プレッシャーなく学習に向き合えます。
- 勉強だけでなく、心の支えにも 家庭教師は、子どもが“安心して話せる大人”の一人になることも。話を聞いてもらう中で、少しずつ自信や安心感を取り戻す子も多くいます。
- 生活リズムの安定につながる 定期的に家庭教師と会うことで、生活にリズムが生まれます。起床や食事のタイミング、勉強時間の習慣化にも良い影響があります。

◉「家庭教師のアーチ」の支援事例紹介
たとえば、
- 中学1年生の男の子:
人間関係で不登校になったが、週2回の家庭教師との学習で「話せる相手」ができ、徐々に自信を取り戻し、現在は別室登校へ。 - 小学5年生の女の子:
発達特性による集団生活の難しさから不登校。家庭教師が図を使った説明や対話を中心にサポートし、学習意欲が回復。
このように、学習支援と心のケアを両立できるのが、家庭教師の強みです。

◉ 家庭教師を選ぶ際のポイントと注意点
- 子どもとの相性が第一。体験授業で雰囲気を確認する
- 発達や不登校への理解がある講師かどうかをチェック
- 短期的な結果より「安心できる学習環境づくり」を重視する
家庭教師は、子どもが「また誰かと関わっても大丈夫かも」と思える小さな一歩になることもあります。
▼アーチの不登校サポートとは?

9. よくある質問(不登校の子を持つ親御さんから)

Q. 勉強をさせるのはまだ早いですか?

「今は心の回復を優先したほうがいいのでは…」という声も多く聞かれます。 もちろん、無理強いは逆効果になりますが、「勉強=やってはいけないこと」と思い込ませてしまうと、あとで再スタートが難しくなります。
本人の気持ちを尊重しつつ、「5分だけ一緒に読んでみようか?」「好きな教科からでいいよ」と軽い形で始めてみるのも一つの方法です。

Q. 家庭教師ってどんな子にも合うの?

一律に「家庭教師がベスト」とは言えませんが、
・人付き合いが苦手な子
・学校のペースに合わない子
・自分の話を聞いてほしい子 には、個別で寄り添う家庭教師が合っていることが多いです。
無料体験などを通して「子どもが安心できるかどうか」を見極めましょう。

Q. 家庭教師を頼むタイミングはいつがベスト?

「学校に戻ってからにしよう」と考える方もいますが、実は「まだ通っていない時期」こそチャンスです。
生活リズムの改善や、少しずつ勉強への苦手意識を和らげることが、不登校の長期化を防ぐきっかけになるからです。
早めにスタートするほど、選択肢は広がります。
10. コラム:親としてできること、できないこと
子どもが不登校になると、「自分の育て方が悪かったのかもしれない」と自責の念に駆られる保護者の方も少なくありません。
しかし、親ができることには限りがあります。逆に、「何でもかんでも親が解決しなければ」と思い詰めることが、親子ともに苦しくなる原因になることも。
大切なのは、
- 親が「味方である」という安心感を持たせること
- 子どもの気持ちを先回りして代弁せず、本人のペースを尊重すること
- 必要に応じて、学校や外部支援とつながる“頼る力”を持つこと
家庭教師やカウンセラーといった「第三者」がいることで、子どもも親も少し肩の力を抜くことができます。
「自分一人で抱え込まなくていい」——それが、最初の回復の一歩になるのです。

11. まとめ|子どもの不登校と向き合うために大切なこと
不登校の原因は、いじめや学習のつまずき、心の問題、家庭や学校の環境など、多岐にわたります。
すぐに解決するものではありませんが、大切なのは「子どもの気持ちを否定せず、寄り添い続けること」。
「学校に行くこと」だけをゴールにせず、「子どもが安心して過ごせる場所を増やす」ことを意識してみてください。
そのための一歩として、家庭教師を活用するのも有効な手段です。
「家庭教師のアーチ」では、不登校の子どもたちに寄り添いながら、学習と心の両面をサポートしています。
興味がある方は、まずは無料体験からお気軽にご相談ください。
▼アーチの無料体験レッスンの詳細はコチラ