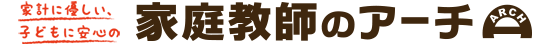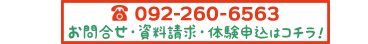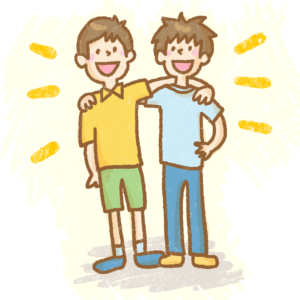【2025年版】不登校の中学生|男子・女子それぞれの特徴・原因・親ができる支援と回復へのポイント
こんにちは!「家庭教師のアーチ」代表の白岩です。
今回のブログは「不登校の中学生をもつ親が知るべきコト」について「男子・女子それぞれの不登校になる特徴や傾向」も含めてお話ししていこうと思います。

不登校の中学生をもつ親が知るべきコト
このページを見て頂いている保護者の方はタイトルにもあるように、不登校状態にある中学生のお子さまをお持ちの保護者の方がほとんどではないかと思います。
小学生時代から不登校のケース、中学生になってから不登校になったケース、中にはまだ不登校ではないけれど「このままだと不登校になってしまうのでは…」と色々なケースがあるかと思います。
不登校という状態は、お子さま本人はもちろん、保護者の方も大きな不安と日々戦っておられるのではないかと思います。
今回のブログでは、少しでも不登校についての不安が軽減するように、不登校に対する知識やお子さまとの接し方など、色々な角度から不登校についてのお話ができればと思っていますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

▼もくじ
1.不登校とは何?
まずは「不登校」とは何か?その定義から考えてみましょう。
えっ?「不登校=学校に行かない事」じゃないの?と思われるかもしれませんが、実は「不登校」にも細かい定義があるんです。
文部科学省によると…
「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
と定義されています。
この定義から考えると「病気や経済的な理由」の場合は不登校には該当しませんし、年間の欠席日数が30日未満の場合も不登校には該当しません。
この定義を前提として、
- 不登校児童の人数はどのくらいなのか?
- 不登校になったきっかけにはどのような理由があるのか?
についてお話ししていきたいと思います。
2.中学生の不登校児童数の推移
最新の中学生の不登校児童数の推移について、文部科学省の調査データ(2023年度)によると、令和5年度(2023年度)は約34万6千人(不登校率:約6.0%)。前年度比で 約4万7千人増加しており、過去最多となっています。
増加の背景としては、コロナ禍以降、学校行事や日常活動の制限により、生活リズムの乱れや交友関係の構築が難しくなったこと、精神的なストレスや不安の増加が、不登校につながるケースが増えていると考えられます。10年前と比較して、中学生の不登校児童数は 約1.8倍 に増加しています。

3.中学生が不登校になるきっかけは?
最新の文部科学省の調査によると、中学生が不登校になる主なきっかけは以下の通りです。
- 無気力・不安(約52.2%)
- 生活リズムの乱れ、遊び・非行(約10.7%)
- いじめを除く友人関係の問題(約10.6%)
無気力・不安とは、成績が上がらないことによる自己評価の低下、将来への漠然とした不安、過去の失敗やトラウマによる自己否定感などが原因になることが多いようです。
また、いじめを除く友人関係の問題は、グループに馴染めず感じる孤立感、小学校時代からの友人が新しい友達を作り、自分が「置いてけぼり」になる感覚、思春期特有の自己意識の高まりで「嫌われているのでは?」と過剰に考えることが原因になることが多いようです。

4.男子と女子で特徴や傾向はある?
男子中学生が不登校になる原因
(1) 学校生活への不満やストレス
- 競争やプレッシャー
体育や授業での競争意識が強く、負けることへのストレスや劣等感を抱きやすい。
- 例: 体育の成績や運動能力の違いで自信を喪失。
- 発表やリーダー役を任された際のプレッシャーが大きい。
- 人間関係のトラブル
男子特有の「上下関係」や「仲間意識」のプレッシャーに悩む。
- 例: グループでの孤立感、リーダーに従うことへのストレス。

(2) 非行やネット依存
- 非行
友人関係や家庭環境が原因で不良行為に走り、不登校につながる。
- 例: 学校内での小さなルール違反がエスカレートし、教員との関係悪化で登校拒否。
- ゲームやネットへの依存
男子に多い特徴として、オンラインゲームやSNSへの依存が挙げられる。
- 夜更かしや生活リズムの乱れ、ゲーム内のコミュニティでの充実感が原因で学校に行く意欲を失う。

(3) 学業成績への不安
- 勉強への苦手意識
男子は女子と比べ、勉強への集中力が持続しにくい傾向がある。
- 理解が遅れることで「自分はできない」と感じ、不登校につながる。
- 特に中学に進学後、科目数が増えてついていけなくなるケースが多い。

(4) 心理的な問題
- 発達特性や行動障害
男子は注意欠陥・多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)などの発達特性を持つ割合が高いとされています。
- 授業中の集中が難しい、ルールを守れないなどが原因で教師や同級生とのトラブルが起こりやすい。
- 感情の抑圧
男子は感情を言葉にすることが得意でない場合が多く、ストレスをため込む傾向があります。
- 周囲に助けを求められないまま、無気力や不安が悪化し、不登校につながる。

女子中学生が不登校になる原因
(1) 複雑な人間関係
- 友人グループ内でのトラブル
- 女子は男子に比べて友人関係が密接かつ排他的になりやすい傾向があります。
- 「グループ内での意見の相違」「特定の子から無視される」などが原因で、居場所を失うことが多い。
- 例: 「〇〇さんと話したら仲間外れにされる」といった無言のルールやプレッシャー。
- 表面化しづらい「いじめ」
- 身体的ないじめよりも心理的ないじめ(陰口、仲間外れ、無視)が多い。
- 周囲に相談しにくく、一人で悩みを抱えがち。

(2) SNSやネットいじめ
- SNSによるプレッシャー
- グループチャットやインスタグラムでの「いいね」「コメント」の数など、SNS特有の競争や評価がストレスになる。
- SNS上でのいじめや、投稿に対する誹謗中傷で心理的ダメージを受ける。「既読スルー」問題
- メッセージを既読にしたのに返信しない、あるいは返信が遅いことで不安や怒りを感じ、関係が悪化。

(3) 心理的要因
- 自己評価の低下
- 女子は思春期に入ると、見た目や成績、他者からの評価を過剰に気にする傾向があります。
- 例: 「太っている」「頭が悪い」といった自己否定感が強まり、不登校のきっかけに。
- 完璧主義
- 勉強やクラブ活動、家庭での役割を完璧にこなそうとし、プレッシャーを抱える。
- 例: 「成績が落ちたら親にがっかりされる」「リーダーとして失敗できない」。
- 思春期特有の情緒不安定
- ホルモンバランスの変化による感情の起伏が激しくなり、小さなトラブルを大きく受け止めがち。

(4) 家庭環境の問題
- 親子関係のストレス
- 親からの過干渉や過度な期待が原因で、自立を求める気持ちとの間で葛藤。
- 特に母親との関係が悪化すると、不登校につながるケースが多い。

| カテゴリー | 要因 | 具体例 | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 学校生活への 不満やストレスー | 競争やプレッシャー | 体育の成績や運動能力の違いで自信を喪失、 発表やリーダー役のプレッシャー |
| 人間関係のトラブル | 男子特有の上下関係や仲間意識のプレッシャー (例: グループでの孤立感) | ||
| 非行やネット依存 | 非行 | 学校内のルール違反がエスカレート、 教員との関係悪化 | |
| ゲームやネットへの依存 | 夜更かしやゲーム内の充実感で 生活リズムが乱れる | ||
| 学業成績への不安 | 勉強への苦手意識 | 理解が遅れることで自己評価が低下、 科目数増加に対応できない | |
| 心理的な問題 | 発達特性や行動障害 | 集中が難しく、教師や同級生との トラブルが発生 | |
| 感情の抑圧 | 感情を言葉にできず、無気力や不安が 悪化 | ||
| 女子 | 複雑な人間関係 | 友人グループ内でのトラブル | グループ内で意見の相違や無視、 無言のルール(例: 仲間外れ) |
| 表面化しづらい『いじめ』 | 陰口や仲間外れ、一人で悩みを抱えがち | ||
| SNSやネットいじめ | SNSによるプレッシャー | いいねやコメント数の競争、 投稿に対する誹謗中傷 | |
| 既読スルー問題 | 既読スルーや返信の遅れが 原因で不安や怒りが発生 | ||
| 心理的要因 | 自己評価の低下 | 見た目や成績、他者評価を気にし 自己否定感(例: 太っている) | |
| 完璧主義 | 成績や家庭内の役割への プレッシャー(例: リーダー失敗の恐怖) | ||
| 思春期特有の情緒不安定 | ホルモンバランスの変化で 感情の起伏が激しくなる | ||
| 家庭環境の問題 | 親子関係のストレス | 親の過干渉や期待による葛藤、 母親との関係悪化 |
5.親がすぐにできる4つの行動
1. 子どもの話を静かに聞く
- 具体的に
子どもが話し始めたときは、遮らず最後まで聞く。アドバイスは控え、「そう感じているんだね」と気持ちに共感する。
- 例: 「学校が嫌だって感じてるんだね。それは辛かったね。」
- ポイント
子どもが安心して自分の気持ちを表現できるようになると、信頼関係が深まります。

2. 学校へのプレッシャーをかけない
- 具体的に
「いつ学校に行くの?」と聞かず、「今はゆっくり休んでいいよ」と伝える。子どもの気持ちを尊重する。
- 例: 「学校に行けるようになるタイミングは、あなたが決めていいんだよ。」
- ポイント
学校復帰を焦らず、子どもがプレッシャーを感じない環境を整える。

3. 日常生活のリズムを整える
- 具体的に
規則正しい生活をサポートするために、毎日同じ時間に起きる・寝る習慣を促す。家族で一緒に散歩や軽い運動をする。
- 例: 「朝ごはんを一緒に食べよう」「少しだけ外を歩いてみない?」
- ポイント
健康的な生活リズムが整うと、心と体の安定にもつながります。

4. 子どもの好きなことを応援する
- 具体的に
子どもの趣味や特技に目を向け、やりたいことを応援する。新しいことに挑戦する場を提供する。
- 例: 「ゲームが好きならプログラミングを試してみない?」「絵を描くのが上手だね!絵画教室に行ってみたら?」
- ポイント
好きなことに取り組むことで、自信と自己肯定感を育む手助けになります。

▼関連記事
6.不登校から立ち直った中学生の実例や保護者の声
実例1: 子どもの話を静かに聞くことで安心感を与えたケース
- 背景
中学2年生の男の子が、学校での友人関係のストレスから登校を拒否。話しかけても黙り込む日が続いていた。 - 親の行動
無理に原因を聞き出さず、「何かあればいつでも話してね」と声をかけ続けた。ある日、子どもがポツリと「クラスで孤立している」と話し始めた。親は「それは辛かったね」と共感する言葉を繰り返した。 - 結果
子どもが徐々に自分の気持ちを話すようになり、1か月後には週1回登校する意欲を見せるように。

実例2: 学校へのプレッシャーをかけないことで復帰を支援
- 背景
中学1年生の女の子が「授業についていけない」と悩み、登校を渋るように。親が「いつ学校に行くの?」と聞くたびにイライラする様子だった。 - 親の行動
「学校に行かなくても大丈夫。今は家でゆっくり休もうね」と伝え、勉強を強制せず一緒にテレビや料理を楽しむ時間を作った。 - 結果
子どもはリラックスした表情を取り戻し、数週間後には「クラスの友達と話したい」と言い出し、登校を再開。

実例3: 日常生活のリズムを整えた成功例
- 背景
中学3年生の男の子が夜更かしと昼夜逆転生活に陥り、不登校に。親は何度も「早く起きなさい」と叱っていたが効果がなかった。 - 親の行動
毎朝決まった時間に一緒に朝食をとることから始め、次に「家の周りを一緒に散歩しよう」と誘った。徐々に起床時間を早める工夫を続けた。 - 結果
健康的な生活リズムが戻り、「体が楽になった」と子ども自身が気づき、翌月から少しずつ登校を再開。

実例4: 子どもの好きなことを応援した結果
- 背景
中学2年生の女の子が、クラスでのトラブルで不登校に。家ではゲームばかりしていたが、親は「またゲーム?」と批判してしまっていた。 - 親の行動
子どもの興味に目を向け、「ゲームのストーリー作りが好きなら、プログラミングに挑戦してみない?」と提案。プログラミング教室を一緒に探した。 - 結果
教室で新しい友達ができ、ゲーム制作を通じて自己肯定感が向上。学校復帰も自然に進んだ。

実例5: 専門家のサポートを活用したケース
- 背景
中学1年生の男の子が、学業へのプレッシャーで不登校に。親が自分たちだけで解決しようと頑張るも、改善の兆しが見えなかった。 - 親の行動
家庭教師やカウンセラーに相談し、専門家のアドバイスを受けながら子どもと接する方法を見直した。家庭教師は子どものペースに合わせた学習支援を行った。 - 結果
学習の遅れを取り戻しつつ、親子の会話も増え、徐々に登校できるように。

7.状況に合わせた支援を受けることが大切!
①学習支援(不登校の原因が学習への不安の場合)
不登校の中学生には、学習に対する不安や苦手意識がある場合があります。その場合は、学習支援を行うことが大切です。家庭教師や塾、学校のカウンセラー、相談窓口などがあります。
中学校の教科書や授業内容を把握し、基礎的なことから学習を進めることで、自信をつけることができます。

②カウンセリング(不登校の原因が分からず漠然と不安な状況の場合)
中学生の不登校の原因はさまざまです。カウンセリングにより不登校の原因を探り、問題解決の手段を提供することが有効です。カウンセリングを受けることで、子供が抱えるストレスや心理的な問題について話すことができます。

③健康管理(不登校の原因が体調不良の場合)
中学生の不登校の原因には、体調不良がある場合があります。健康管理を行い、睡眠や食事、運動などを適切に行うことで、体調面の問題を解決することができます。
専門的な知識が必要になるケースも多いため、医師による診断や治療を受けることで、早期に体調を回復することができます。正式に「病気」と診断されれば、不登校に含まれない場合もあります。

以上のようなアプローチを組み合わせ、状況に応じた不登校支援を行うことで、不登校の中学生をサポートすることができます。
8.家庭教師のアーチによる支援事例(保護者の声)
最後になりますが、家庭教師のアーチの支援事例と利用された保護者の声をいくつか紹介させて頂きます。学習支援の選択肢としてご検討いただけますと幸いです。
1. 学習面での自信を取り戻したケース

息子は不登校になってから勉強に全く手を付けられず、自分の将来を悲観していました。
家庭教師の先生が基礎から丁寧に教えてくれたことで、少しずつ解ける問題が増え、『自分にもできるんだ』と前向きな気持ちになったようです。
今では、自分から勉強を始める姿も見られるようになり、とても感謝しています。
2. 心の安定をサポート

娘は友人関係のトラブルで不登校になり、家でもほとんど話さない日々が続いていました。
家庭教師の先生は勉強だけでなく、娘が好きな話題を振りながら、ゆっくりと信頼関係を築いてくれました。
娘が笑顔で話す姿を久しぶりに見て、私も安心しました。
3. 生活リズムの改善ができたケース

娘は学校での失敗が原因で自己否定感が強まり、不登校になりました。
家庭教師の先生が娘の得意な英語を褒めて伸ばしてくれたことで、『自分にはこれが得意だ』と思えるようになったようです。
娘が少しずつ自信を取り戻していく姿を見て、本当に感謝しています。
4. 高校受験のサポートで成功したケース

受験を控えていた息子がプレッシャーで不登校になり、家でもどう声をかければいいか分からず悩んでいました。
家庭教師の先生が受験計画を具体的に立ててくれ、息子に寄り添いながら勉強を進めてくれたおかげで、無事志望校に合格することができました。
息子が『先生がいなかったら無理だった』と言っていました。本当に感謝しかありません。
いかがでしたでしょうか?
不登校はお子さまはもちろん、保護者の方々も大きな不安を抱えながら日々過ごされているかと思います。
「このままで進学できるのか?」「将来は大丈夫なのだろうか・・・」など、色々と心配は尽きないですよね。。。
家庭教師のアーチでは、不登校のお子さまを数多くお預かりしております。
学習支援だけではなく、親には話せない悩みや相談などを聞いてあげることで、お子さんのストレスや不安を軽減することも出来るかと思います。
不登校のお子さまをお持ちの保護者の方で「家庭教師」という形式の支援に興味をお持ちの方は気軽にご相談ください。