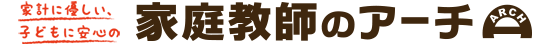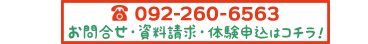【セルフチェック付き】高校生が発達障害を診断する前に知るべき6つのこと
「高校生になってから学習や人間関係で苦労し始めた」「もしかして発達障害かもしれない」と感じている方や保護者の皆さん、本記事では診断までの流れやセルフチェック、そして学習支援の重要性をわかりやすくまとめています。
特に「家庭教師のアーチ」では、発達障害の特性に配慮した個別指導やメンタル面でのサポートが受けられるのが大きな特徴です。

この記事を読むとわかること
- 高校生に多い発達障害の特徴や診断を考えるタイミング
- 病院やスクールカウンセラーへの相談方法と具体的な流れ
- セルフチェックを活用した自己理解の深め方
- 学習支援の重要性と「家庭教師のアーチ」によるサポート内容
- 診断後に利用できる支援制度や周囲の理解を得るポイント
ぜひ最後までお読みいただき、次のアクションを見つけてみてください。
▼もくじ
1. 高校生の発達障害とは?増えている背景
思春期に顕在化する発達障害の特徴
発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のかたよりが原因で、コミュニケーションや行動面で特有の困難を抱える状態を指します。小学生の頃はそれほど問題視されなかった学習や対人関係のつまずきが、高校に入ると科目数の増加や人間関係の複雑化によって一気に表面化するケースが多いです。
- 思春期特有の悩みが重なる
部活動や受験などのプレッシャーも加わり、発達障害の特性が強く出ることがあります。 - 情報へのアクセスが容易
スマホやSNSで「発達障害」「診断」「高校生」といったキーワードを調べ、自分の症状と照らし合わせる高校生が増えています。
「もしかして…?」と思ったときには、早めに専門家の診断を検討することが大切です。

2. 診断を考えるタイミングときっかけ
学習成績の急激な低下
- 課題量や難易度の急上昇
中学までは問題なかった学習が、高校のレベルアップにより一気につまずく。 - 注意力・記憶力の課題
発達障害の特性によって勉強のペースが合わず、成績が落ちることも。

対人関係のトラブル
- コミュニケーションのすれ違い
クラスメイトや部活の仲間とうまく関係を築けず、孤立やいじめの原因になるケース。 - 思春期の繊細さ
自己肯定感が下がりやすく、保護者もどう対応していいか悩みがち。

教員やスクールカウンセラーからの指摘
- 学校側のサポート提案
担任やカウンセラーが「学習面や行動面で気になる点」を感じ、保護者に相談を勧める場合があります。

本人や保護者の強い不安
- 集中力が続かない・進路に不安
精神科や児童精神科など専門医を探して受診するきっかけに。 - 早期診断で適切な配慮を
合理的配慮や学習支援につながる可能性が高まるため、一歩踏み出すことが大切です。

3. 主な発達障害の種類と特徴
(1) 自閉スペクトラム症(ASD)
- 特徴
社会性やコミュニケーションに課題、特定の興味・行動への強いこだわり - 高校生での例
グループワークが苦手、部活動で対人ストレスを抱えやすい
(2) 注意欠如・多動症(ADHD)
- 特徴
不注意・多動・衝動性があり、集中力を維持するのが難しい - 高校生での例
提出物の期限管理が苦手、衝動的に行動してしまう
(3) 学習障害(LD)
- 特徴
読む・書く・計算など特定の分野に顕著な困難 - 高校生での例
英語のリーディングだけ異常に苦手、数学の計算が極端に遅い
4. 【セルフチェック】気になる症状は?
以下のチェックリストはあくまで目安であり、正式な診断は専門家による評価が必要です。「多く当てはまる」と感じたら、スクールカウンセラーや医療機関へ相談してみましょう。

不注意(主にADHD)
- 授業や話を聞いているつもりでも、意識が飛んでしまう
- 宿題や提出物の締め切りをしょっちゅう忘れる
- 忘れ物・なくし物が多く、探し物に時間をとられる
多動性・衝動性(主にADHD)
- 授業中や会議中に落ち着いて座っていられない
- 思いついたことをすぐ口に出して後悔することが多い
- 計画を立てるのが苦手で、衝動的に行動してしまう
対人関係(主にASD)
- 相手の表情や冗談が理解しにくく、会話がかみ合わないと感じる
- グループ活動や団体行動で、ペースを合わせるのが苦痛
- 特定の分野への強いこだわりがあり、周囲と話が合わない
学習面(LDを含む)
- 英単語や漢字を覚えるのに極端に時間がかかる
- 数学や物理の公式を覚えられず、点数に大きな差が出る
- 読み書きが遅く、テストやレポートで時間配分がうまくいかない
5. 学習支援の重要性と「家庭教師のアーチ」のサポート
学習支援が必要な理由
- 高校生の学習内容が高度化
中学より科目数が多く難易度が高いため、個別に合ったサポートが効果的。 - 進路選択の大切さ
大学進学や就職など将来を左右する時期だからこそ、適切な支援を受けると自己肯定感を維持しやすい。 - 早期の自己理解
学習面でのフォローを受けながら、自分の得意・不得意を明確にして進路に活かせる。
「家庭教師のアーチ」の
主なサポート内容
 個別指導・オーダーメイド
個別指導・オーダーメイド
カリキュラム
- 一人ひとりの特性や目標に合わせ、柔軟にカリキュラムを組めるので効率が良い。

 カウンセリング的アプローチ
カウンセリング的アプローチ
- 勉強だけでなく、メンタル面にも配慮した指導を行うため、ストレスを軽減しながら学習を継続可能。

 オンライン対応
オンライン対応
- もし対面が難しくても、自宅など安心できる場所でオンライン学習もできる。

 保護者とのコミュニケーション
保護者とのコミュニケーション
- 学習の進捗やメンタルの状態を共有し、必要に応じて方針を修正。保護者も安心してサポートできる。

 進路相談・受験対策
進路相談・受験対策
- 一般入試・推薦入試・AO入試など、さまざまな進路に対応した指導実績が豊富。

▼家庭教師のアーチの発達障害サポート

6. 正しい診断を受けるためのプロセス

1. スクールカウンセラー・教員に相談
学校での様子を共有し、適切な専門機関を紹介してもらう。
2. 医療機関の予約・受診
- 精神科・心療内科・児童精神科などで、発達障害の診断を行える。
- 予約が取りづらい場合もあるので早めに行動を。
3. 多角的な検査・評価
心理検査や保護者・学校関係者へのヒアリングなど、複数の視点から総合的に評価する。
4. 診断結果と支援計画の作成
診断結果を踏まえて、学習面・生活面で必要なサポートや合理的配慮を検討。

Q. 診断にかかる費用は?

A. 一般的に保険適用となるため、数千円~程度が多いですが、検査内容や病院によって異なります。事前に病院へ問い合わせると安心です。
7. 診断後に利用できるサポート・支援制度
- 学校での合理的配慮
テスト時間の延長や座席変更、教材の工夫など、特性に合わせた支援が期待できます。 - 専門家との連携
カウンセリングやソーシャルワーカーなど、外部機関と協力して学習・生活面を改善。 - 特別支援学級・通級指導
学校によっては発達障害に特化したプログラムがあり、個別指導や生活スキルの習得をサポート。 - 障害者手帳の取得(該当する場合)
進学や就職時に活用できる支援制度や手当が受けられる可能性があります。

8. 周囲の理解と本人の心がけ
- 周囲への情報共有
親しい友人や教員に特性を伝えることで、理解やサポートを得やすくなる。 - 自己理解とストレスマネジメント
自分の得意・不得意を把握し、適切な休息やリラクゼーション法を身につける。 - 継続的なサポート体制
家族や指導者、専門家が連携しながら、長期的に学習や生活スキルを伸ばすと安心。

9. まとめと次のステップ
高校生は思春期の真っただ中であり、学業や人間関係で悩みが増える時期です。そこに発達障害の特性が加わると、さらにつまずきが大きくなる場合があります。しかし、正確な診断と適切なサポートがあれば、高校生活や将来の進路は大きく開けていきます。
もし「自分は発達障害かも
しれない」と感じたら?
- セルフチェックを参考にしつつ、スクールカウンセラーや保護者に相談する
- 必要に応じて医療機関を受診し、正しい診断と支援計画を立てる
- 「家庭教師のアーチ」のような専門性の高い学習支援を活用し、学力面・メンタル面のサポートを受ける
早めに専門家へ相談し、周囲と協力しながら対策を進めることで、自己肯定感を高めながら充実した高校生活を送ることが可能です。興味を持たれた方は、一度「家庭教師のアーチ」に問い合わせてみるのも良いでしょう。
▼家庭教師のアーチ(利用者の声)