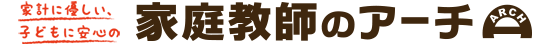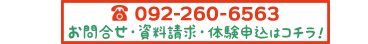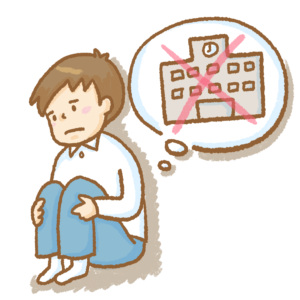【不登校の高校生】原因・親の対応・進路サポートまとめ|2025年版
▼もくじ
はじめに

高校生のわが子が学校に行きたがらない……

単位不足、留年・中退の心配ばかり頭をよぎるけれど、どう対応していいのかわからない
こうした悩みを抱える保護者の方は少なくありません。高校生になってから不登校が始まると、単に勉強の遅れだけでなく、将来設計にも暗い影が差してきます。家族のサポートにも限界があり、場合によっては親自身がメンタル面で追い詰められるケースも珍しくないでしょう。
本記事では、「高校生の不登校」というテーマについて、その主な原因や背景、保護者としてできる具体的な対応策、そして不登校生におすすめの学習サポート(通信制高校・オンライン学習・家庭教師・フリースクールなど)を包括的に解説します。さらに、メンタルケアや親子関係にまつわるアドバイス、よくある疑問に答えるQ&Aコーナーも設けています。
「このままでは学校に行けないだけでなく、家にひきこもったまま将来が閉ざされるのでは……」と不安を感じている方こそ、ぜひ最後までお読みください。状況を改善するための具体的な一歩や相談先がきっと見つかるはずです。

1. なぜ高校生が不登校になるのか:主な原因と背景
1-1. 学力面でのつまずきとプレッシャー
難易度の急激な上昇と単位不足への焦り
中学までは問題なく授業についていけていた生徒が、高校に進学した途端に難易度の高さに苦しむケースは珍しくありません。特に進学校や専門学科に進んだ場合、授業スピードが速い・課題が多い・テスト範囲が膨大……といった状況に圧倒され、「もうついていけない」という気持ちが芽生えてしまうのです。
また、高校は義務教育ではなく単位制が主流なので、一定以上出席しないと単位がもらえません。単位不足が直接的に留年や中退に結びつく現実を前に、強い焦りから登校意欲を失う生徒もいます。
受験や進学サポートへのプレッシャー
高校生になると、保護者や周囲の友人が大学受験・専門学校・就職といった「その先」の進路を具体的に考え始めるため、生徒自身も自然とプレッシャーを受けやすいです。模試の成績が思うように伸びなかったり、成績表に赤点が並んだりすると、「こんな成績では将来が危うい」と自己否定してしまい、学校そのものを拒絶し始めるきっかけになることがあります。

1-2. 人間関係のトラブル:いじめ・孤立・引きこもり
SNS時代のいじめや誹謗中傷
現代では、学校内でのいじめに留まらず、SNSやチャットツールでの誹謗中傷が問題視されています。高校生はスマートフォンを日常的に利用しているため、ネット上での悪口や無視が重大なトラブルに発展しやすいのです。クラスでの悪口がそのままLINEやSNSに波及すると、「居場所がない」と感じて登校拒否になる生徒が増えています。

部活動・クラス内での摩擦や孤立感
高校の部活は練習や試合に時間を割く本格的なものも多く、上下関係や技術レベルの違いがストレスになりがちです。部活内での不協和音がクラス関係にも波及し、他のクラスメイトともうまく馴染めない――という状況は、思春期の高校生にとってかなりの精神的負担です。結果的に引きこもりの状態に陥り、不登校が長期化してしまうこともあります。

1-3. 家庭環境と親子関係の問題
親のストレスと保護者の悩み
子どもが不登校になると、保護者の悩みは想像以上に深刻化しやすいです。「なぜわが子だけが……」という自責の念や、周囲に相談しづらい孤独感、経済的な負担などが重なり、親自身がうつ状態や不安障害を抱えてしまうこともあります。親子関係がぎくしゃくし、家族内でのコミュニケーションまで悪化してしまうケースは決して珍しくありません。
家庭内トラブルが子どもに及ぼす影響
「勉強しなさい」「ちゃんと学校に行きなさい」と強く言いすぎることで、子どもは「自分はダメな存在だ」と思い込みます。また、親同士の不仲や離婚、経済的な問題など家庭内が落ち着かない場合も、子どもが安心して学習や学校生活に向き合えなくなる要因の一つです。思春期という時期は、家族のサポートや肯定感をどれだけ得られるかが大きく影響します。

1-4. 思春期の心理・メンタルヘルス
自己肯定感の低下
高校生は思春期のど真ん中であり、周囲の目や評価を強く意識するあまり、些細な失敗でも大きく落ち込んでしまいがちです。とくに、家や学校での成功体験やポジティブな言葉かけが不足すると、急速に「自分はなんて情けないんだ」と自己肯定感が下がり、不登校に陥るきっかけになります。
心療内科・カウンセリングが必要な場合
不登校が長引き、本人が「学校に行きたいけど行けない」という状態に苦しんでいるときは、うつ状態や不安障害を疑うべきこともあります。心療内科やスクールカウンセラーの力を借りるのは、一つの重要な選択肢です。早期に受診して対処することで、深刻化を防げるケースも多々あります。

2. 不登校が長期化するとどうなる?リスクと早期対応の重要性
2-1. 単位不足・進級問題・中退への直結
高校生の不登校が中学生と決定的に異なるのは、単位取得が必要な点です。長期間休むと、留年や中退という現実的な問題が見えてきます。高校を中退すると、その後高卒認定(大検)を取得するか通信制高校に編入するなど別の手段を取らざるを得ず、進学や就職のルートが限定される可能性が高いです。
2-2. 社会的孤立による将来設計の喪失
不登校が長引くと、学校行事や部活動、友人との交流が失われるだけでなく、社会性を身につける機会が減少します。高校生同士のコミュニケーションから学ぶスキルは大人になってからも必要不可欠ですが、それらを経験できないまま卒業(あるいは中退)を迎えると、将来の就職活動や人間関係にも悪影響が出るかもしれません。
2-3. 親子関係の悪化・家庭内のストレス増大
保護者の方が焦って「行きなさい!」と責めるほど、子どもは心を閉ざし、引きこもり状態が進んでしまうことがあります。お互いがストレスをため合うと、家庭内はさらにギクシャクし、解決の糸口が見えなくなるのです。こうした悪循環は、早期対応を怠った結果として現れることが多く、「もうどうにもならない……」と塞ぎ込む保護者も増えてしまいます。
2-4. 早期対応が鍵:取り戻せる進路・学びのチャンス
一方で、早期対応を行えば、中退や留年を回避したり、適切なサポートによって単位不足を補うなど、リカバリーの方法はいくつも存在します。通信制高校への編入やオンライン学習、家庭教師を活用してコツコツ学力を取り戻す生徒も多くいます。焦らず、しかしタイミングを逃さず行動することが、子どもの将来を大きく左右するのです。

3. 不登校の高校生への対応策:原因と対策をどう結びつける?
3-1. まずは現状を整理:子どもの気持ちを聴く
本人の意思尊重と傾聴姿勢
不登校の原因は人それぞれですが、親ができる最初の一歩は「子どもの気持ちを正面から受け止める」ことです。「なぜ行かないの?」と詰問するのではなく、「今、一番つらいのは何?」と尋ね、子どもの心の声に耳を傾けましょう。反論や批判はNGで、共感や頷きを意識して対話するだけでも、思わぬ本音が出てくるかもしれません。
小さな変化を見逃さず褒める
子どもが部屋にこもりがちな状態から、「今日は少しだけリビングでテレビを見ていた」などの小さな行動を起こしたら、それを大いに肯定してあげてください。些細な一歩を褒められることで「受け入れてもらえた」「自分にもできるんだ」という自己肯定感が生まれます。

3-2. 担任・スクールカウンセラー・心療内科との連携
学校との情報共有
単位不足や留年リスクを把握し、どの程度の登校日数が必要なのか、補習・レポート提出の特例はあるかなど、担任や学年主任と定期的に連絡を取りましょう。学校としても、スクールカウンセラーを介して保護者や生徒と面談できる体制があるはずです。
専門家の力を借りる
メンタルの落ち込みが激しい場合や、本人が強く悩んでいる様子なら、心療内科や精神科の受診、または医療機関と連携するスクールカウンセラーに相談することも視野に入れてください。うつ状態や不安障害が疑われる場合は、プロのサポートが早期回復につながります。

3-3. 生活リズムの立て直しと環境調整
夜型生活から朝型へ少しずつ移行
不登校が続くと生活リズムが乱れ、夜中にスマホやゲームをして昼に起きる生活に陥りがちです。一気に「朝7時に起きろ!」と厳しく言っても逆効果なので、30分ずつ起床時間を早めるなど無理のないペースで改善を図りましょう。

家庭学習スペースの整備
自宅で過ごす時間が増えるほど、部屋が散らかる・勉強するスペースがない、といった問題が出ます。明るい場所に机を移動する、最低限の文具や教材を揃えるなどして、家でも学習に向かいやすい環境をつくりましょう。

4. 不登校の高校生向け学習サポート:通信制高校・オンライン学習・家庭教師・フリースクール
不登校が続くと、「単位はどうなるの?」「卒業できるの?」といった学習面の不安が増大します。しかし、現代には学校以外にも多様な学びの選択肢が存在します。ここでは代表的な4つのサポート手段を紹介します。
4-1. 通信制高校
通信制高校の仕組みとメリット
- レポート学習が中心で、スクーリング(登校)は必要最低限
- 登校日が限られているため、身体的・精神的な負担が少なく済む
- 在籍中にアルバイトや趣味、ボランティアなど、自分のペースで経験が積める
デメリットと注意点
- 自己管理能力が求められる
- 通う回数が少ないため、友人関係がつくりにくく、孤立しやすい生徒も
- 親も情報収集を怠ると、子どもに合わない通信制高校を選ぶリスクがある

4-2. オンライン学習
映像授業・ライブ指導
塾や予備校、学習サービスが提供するオンライン講座は、在宅で受講できるため、登校が難しい時期でも学力の遅れを取り戻せる手段として注目されています。ライブ形式で講師やチューターに質問しながら進めるシステムもあり、コミュニケーションを取りつつ学習を進められるメリットがあります。
成功の鍵は自己管理+コーチング
オンライン学習は時間や場所に融通が利く反面、自己管理ができないとサボってしまうリスクがあります。保護者が進捗を確認する、コーチやチューターが学習スケジュールを見守ってくれるなど、適度なサポートを得られる形が理想です。

4-3. 家庭教師
マンツーマン指導の強み
不登校で集団の中に入ることが難しい子どもでも、家庭教師なら1対1のコミュニケーションが可能です。学習レベルや得意・苦手科目に合わせたオーダーメイドのカリキュラムが組めるため、効率よく学力を補強できます。
メンタル面でもメリット
家庭教師の先生が定期的に来てくれると、社会との接点が保たれるのも大きな利点。勉強以外の悩み相談に乗ってもらうことで、子どもが少しずつ自信を取り戻すケースも多くみられます。親子関係に行き詰まりを感じている保護者には有力な選択肢です。

4-4. フリースクール
学校外の居場所を提供
フリースクールとは、不登校や引きこもりの子ども・若者が集まって学習やコミュニケーションを行う民間施設です。必ずしもカリキュラムが厳密に決まっているわけではなく、自分の興味をもとに自由に活動できるプログラムが多いのが特徴です。
社会的なつながりを取り戻す
同じような悩みを抱える仲間と出会えるため、孤立感を減らし、「自分は一人じゃないんだ」と感じられる効果があります。フリースクールによっては、通信制高校と提携し、単位取得をサポートしているところもあるので、学びと居場所の両面をカバーしやすい選択肢と言えるでしょう。

5. 家庭教師のアーチができること:不登校の高校生サポート
5-1. 不登校生への指導実績・専門ノウハウが豊富
「家庭教師のアーチ」は、長年にわたり不登校や引きこもり状態の生徒にマンツーマンで学習指導を行い、解決へ導いてきた豊富な実績があります。指導前の面談で保護者と生徒の抱える悩み・学習状況を丁寧にヒアリングし、そのうえで一人ひとりの個性に合った指導スタイルを提案。勉強だけでなく、心のケアにも配慮した対応が好評です。

5-2. オンライン・対面のハイブリッド対応
- オンライン学習
対面形式の受講が難しい、生徒の状態によってはまずオンラインで慣れるところからスタートできます。ビデオ通話を活用し、直接対面しなくても授業を受けられるのが魅力です。 - 対面指導
少しずつ人と接することに抵抗がなくなれば、対面指導に切り替えてさらに密度の濃いサポートを行います。オンラインと対面を組み合わせる“ハイブリッド指導”で、状況に応じたベストなアプローチを選べるのが強みです。

5-3. 進路相談からメンタル面のフォローまで
- 通信制高校や高卒認定のサポート
不登校が長期化して全日制への復帰が難しくなった場合、「通信制高校へ転校して単位を取得する」「高卒認定(大検)を受けて大学受験を目指す」など、さまざまな道があります。家庭教師のアーチでは生徒と保護者が納得できる形で進路を考えられるよう支援します。 - 必要に応じた保護者との連携
指導中に生徒のメンタル面で不安が見られる場合、必要に応じて保護者の方と相談をする機会を設け、なるべく早い段階で解決策を提案することができます。

6. 不登校の高校生を支える保護者が気をつけたいこと
6-1. 「厳しく叱る」より「家族のサポート」を
不登校になる背景には、単なる「怠け」では済まされない複雑な事情があることが多いです。ときには部屋から出られず、勉強がまったく手につかない子どもに向かって「ちゃんとしなさい!」と叱ってしまうと、追い詰める結果にしかなりません。叱咤激励が功を奏するケースは少なく、むしろ子どもの自己肯定感を一層傷つけてしまう可能性があります。
6-2. 親のストレスケアと相談窓口の活用
保護者として、仕事や家庭を切り盛りしながら不登校の子どもを支えることは容易ではありません。どうしても心身の疲労が溜まり、「もう限界かもしれない」と感じることがあるでしょう。そのようなときは、自治体の教育相談やカウンセリング、NPOの相談窓口などを活用し、親自身もサポートを受けることが大切です。
6-3. 周囲と比較しすぎず、本人の意思を尊重
学校に通えているクラスメイトや、スムーズに受験勉強を進めている子と比べると、「どうしてうちの子は……」と感じるのも無理はありません。しかし、不登校の原因は人それぞれ。周囲との比較で焦るよりも、「今の状態でできることは何か」を一緒に考え、小さなステップを積み重ねていく方が結果的にスムーズな回復につながりやすいです。

7. Q&A:不登校の高校生が抱える疑問に答えます

Q1. 不登校が半年以上続いています。もう留年覚悟で学校を辞めるべきでしょうか?

A: 焦って中退を選択する前に、まずは学校に在籍しながら補習やレポート提出などで単位を認定してもらえないか、担任や学年主任に相談してみましょう。
通信制高校への転校や、フリースクールを併用して単位をカバーできる可能性もあります。早期対応を始めれば、意外と救済措置があるケースも多いです。

Q2. 親として心療内科を受診させたいのですが、拒否された場合どうしたらいい?

A: 子どもが強い拒否感を示す場合は、一緒に行くのではなく、まずは親が相談窓口として病院やカウンセラーに自身の悩みを打ち明ける方法があります。そこで専門家と話す中で、子どもにどのように受診を促せばよいかアドバイスを得ることも可能です。無理強いだけは避けましょう。

Q3. 留年や中退になったら大学受験は不利ですか?

A: たしかに一般的な印象では不利に思われるかもしれませんが、高卒認定(大検)を取得して大学に進む生徒も多数存在します。また、通信制高校で着実に単位を積み重ねて合格を勝ち取る例もあります。試験科目や学習の進め方をきちんと工夫すれば、逆転合格も決して夢ではありません。

Q4. 家庭教師をつけたいけれど、費用面が心配です。

A: 家庭教師は一般的に費用が高いイメージがありますが、指導回数や科目数を調整し、予算に合わせる相談ができる場合が多いです。「家庭教師のアーチ」では無料体験を行っているため、まずは気軽にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
自治体やNPOの支援制度も探してみると、利用できる助成が見つかるかもしれません。
8. まとめ:不登校の高校生をもう一度前向きにするために
高校生の不登校には、学業面のプレッシャー、人間関係のトラブル、家庭環境、思春期特有の心理的要因など、多様な要素が絡んでいます。単位不足や進級問題がリアルに迫るため、不登校が長期化すると留年や中退という選択肢が視野に入ってくる点が大きな特徴です。
しかし、通信制高校・オンライン学習・家庭教師・フリースクールといった代替の学びの場も豊富に存在し、早期対応さえ行えば道は残されています。保護者は焦りすぎず、子どもの気持ちを尊重しながら、必要に応じて専門家やサポート機関に相談してください。家庭教師のアーチなどのサービスを活用すれば、学力面だけでなくメンタルケア、進路相談までトータルで対応してもらえます。

9. 「家庭教師のアーチ」にまずは無料相談を:行動を起こすなら今
もしお子さんが不登校状態で、「どのようにサポートしたらいいのかわからない」「通信制高校や高卒認定について相談したい」といったお悩みがあるなら、ぜひ「家庭教師のアーチ」にご相談ください。
家庭教師のアーチのサポート
- 不登校の高校生指導実績が豊富
これまで数多くの生徒をサポートしてきたノウハウがあるので、学習面の遅れだけでなくメンタル面や社会的スキルの回復まで、きめ細かいアプローチを実施。 - オンライン・対面のハイブリッド指導
最初はビデオ通話から始める、生徒の状態がよくなれば対面に移行するなど、柔軟にプランを設計。自宅にいながらも充実したサポートが受けられます。 - 進路相談や高卒認定対策にも対応
不登校が長期化していても、通信制高校や高卒認定(大検)を利用して再び大学受験や専門学校進学を目指せます。保護者と一緒にスケジュールを組み、実現可能なプランを提案。
行動を起こすこと自体が勇気のいるステップですが、早めの相談が「子どもの未来」を大きく変える可能性があります。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、親子で新たな一歩を踏み出してください。