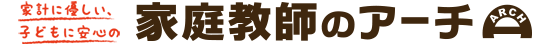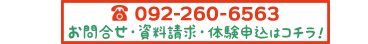中学生の不登校でも高校進学は可能|安心できる選び方と対策ガイド
▼もくじ
不登校でも高校に行けるの?
「中学生のうちに不登校になってしまったら、高校に行けないのではないか」と考え、進路をあきらめかけている方は少なくありません。しかし、結論から言えば、不登校の生徒でも高校進学は十分に可能です。近年、多様な事情を抱える生徒を受け入れる高校が増え、定時制や通信制、サポート校など、多様な学習スタイルを選択できる時代になっています。
例えば、出席日数や内申点が足りない場合でも、面接や作文、実技などを重視する特色入試で合格を勝ち取るケースもあれば、最初から通信制・定時制に的を絞り、学び直しをしやすい環境でゆっくりと学力を伸ばしていく人もいます。
不登校という状態にとらわれすぎず、「自分に合った学び方」を見つけることで、高校での新しい生活をスタートさせる道はいくらでもあるのです。

高校進学についての悩み
ここでは、不登校の生徒本人や保護者がよく抱える代表的な不安や疑問を整理してみましょう。
1.出席日数が足りないのでは?
通常の全日制高校の場合、中学時代の出席日数や内申点が合否を大きく左右することは事実です。ただし、それだけが合否を決定するわけではなく、学校によって基準や評価ポイントが異なります。最近では、不登校の期間がある生徒でも受け入れ実績のある高校も増えています。
2.高校についての情報収集はどうすればいい?
不登校になっていると、学校の先生や同級生とのコミュニケーションが減り、進路に関する情報が入りにくい状況に陥りがちです。しかし、通信制や定時制をはじめ、不登校の受け入れに積極的な高校は公式サイトやパンフレット、個別相談会などを通じて情報を発信しています。また、教育相談所やフリースクール、NPO法人、家庭教師のアーチなどのサービスを利用して情報を得るという方法もあります。
3.保護者に迷惑をかけてしまうのでは?
不登校の生徒本人は「自分のせいで親に負担をかけているのではないか」という罪悪感やプレッシャーを抱えていることが多いです。しかし、将来の進路を一緒に考えるうえで、保護者と本人が情報を共有しながらサポートを受けることは非常に大切です。むしろ早期に動き出すことで、不要なストレスを軽減できる場合も少なくありません。

▼ この記事でわかること
- 不登校でも高校進学できる理由と、具体的な選択肢の概要
全日制・定時制・通信制・サポート校など、それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理します。
- 高校進学に向けた準備や受験勉強の進め方
オープンスクールの活用や面接・作文対策、オンライン学習や家庭教師の利用など、不登校でも取り組みやすい学習方法を紹介します。
- 実際に不登校から高校進学した人たちの事例や体験談
成功体験を知ることでモチベーションを高め、不安を解消する手がかりになります。
- 進学後のサポートや、保護者ができる支援策のポイント
入学して終わりではなく、在学中のフォローやメンタルケアをどう確保するか、周囲とどう連携していくかも重要です。
- 家庭教師サービス「家庭教師のアーチ」を利用するメリット
不登校生徒向けの指導実績やサポート体制が充実している家庭教師サービスの活用法を具体的に解説します。

【背景】不登校が増加している現状と理由
不登校生徒数の推移と社会的背景
文部科学省の調査によると、中学校における不登校(「年間30日以上欠席」の状態)の生徒数は年々増加傾向にあります。ある年度には中学生の不登校生徒数が10万人を超えたという報告もあり、決して少ない数字ではありません。昔は不登校が「特別なケース」だと思われていましたが、現代では「誰にでも起こりうるもの」として認識が広がりつつあります。
要因としては、SNSやスマホの普及に伴うコミュニケーションの変化、情報過多によるストレス、家庭環境の多様化など、さまざまな社会的背景が挙げられています。また、新型コロナウイルスの流行によってオンライン学習が広まった一方で、学校との接点が薄れ、学習意欲や人間関係に不安を抱える生徒も増えているとも言われています。
不登校の要因と多様化
1.学業不振
勉強についていけない、授業のスピードが速すぎる、クラスメイトとの差を感じて自己肯定感が下がる、などがきっかけで登校をしぶるようになるケースです。とくに英語や数学といった積み重ねが重要な教科でつまずくと、一気に苦手意識が強まりやすいです。

2.人間関係のトラブル
いじめや友人関係、部活の上下関係、先生との対人関係など、学校内での人間関係が原因となるケースも少なくありません。特に中学生は思春期の真っ只中であり、些細なトラブルが大きな精神的負担になることがあります。

3.家庭環境の変化
親の転勤や離婚、経済的な困難、兄弟の進学や受験など、家庭内で大きな変化が起きると子どもが心理的に不安定になり、それが不登校につながる場合もあります。

4.体調不良・精神的な問題
うつ状態や不安障害、発達障害の特性に気づかれないまま学校生活を続けると、本人に大きな負荷がかかります。朝起きられない、頭痛や腹痛が続く、強いだるさを感じるなどの症状があるときは、単なるサボりではなく専門機関への相談が必要かもしれません。

5.オンライン環境の影響
近年はSNSやオンラインゲームなど、家にいながら外部とつながれる環境が発達しました。一方で、学校内の人間関係にわずらわしさを感じ、自宅のネット環境に引きこもる形で不登校が長期化するケースも存在します。

進学希望率との関係
日本の中学校から高校への進学率は90%以上と非常に高い水準です。不登校の生徒であっても、「高校には行きたい」という思いを捨てきれない人は多く存在します。実際、不登校を経験しながらも高校に進学し、その後大学や専門学校へと進んでいる例は数えきれないほどあります。
一方で、「不登校=もう高校進学は難しい」という固定観念から、最初から進学をあきらめてしまうケースも少なくありません。こうした誤解を解消し、多様な選択肢を知ってもらうことこそが、この記事の大きな目的でもあります。
不登校でも受験できる高校の種類と特徴
不登校を経験している生徒が高校進学を考えるとき、まず知っておきたいのが高校の多様な形態です。一般的には全日制高校が思い浮かびますが、実は通信制や定時制、さらにサポート校と提携している学校など、学び方は一つではありません。それぞれの特徴を理解し、自分のニーズに合った選択をすることが大切です。
1.全日制高校
出席日数の評価方法
全日制の高校は、平日の朝から夕方まで毎日授業がある、いわゆる「普通科」のイメージが強い学校形態です。
中学時代の出席日数や内申点、学力テストの結果が重要視されることが多いですが、学校によっては不登校期間があっても柔軟に評価する「特色選抜」や「推薦入試」を設けています。
例えば、面接重視の学校では、「不登校の期間に何を考え、どんなことを学んだか」を率直に伝えることでプラスに評価されることもあります。最近は、生徒の多様な背景を積極的に受け入れる私立高校も増えているため、全日制を検討する際には幅広く情報を集めてみましょう。
一般入試・推薦入試それぞれのメリット・デメリット
一般入試
メリット
学力試験が主体のため、出席日数や内申点に自信がなくても、試験当日の得点がよければ合格の可能性が高まる。
デメリット
学力試験の範囲が広く、集中的な受験勉強が必要。特に不登校期間が長いと、学習ペースを取り戻すのに時間がかかることも。

推薦入試
メリット
内申点や面接、作文など、多角的に評価されるケースが多い。学力テストよりも「今後の意欲」を重視してくれる学校もある。
デメリット
学校ごとの基準が曖昧な場合もあり、過去の不登校期間について詳しく聞かれることもある。推薦枠が少なく競争率が高いケースもあるため、事前調査が重要。

2.通信制高校
学習スタイルの多様化
通信制高校は、自宅学習を中心とし、定期的にレポートを提出し、スクーリング(登校日)や試験に参加して単位を修得していくスタイルが一般的です。最近はオンライン授業を導入している学校も多く、地方に住んでいても都市部の通信制高校に通える仕組みが整いつつあります。
自分のペースで学べるメリット
- 週数回や月数回など、登校の頻度が選べる
- アルバイトや習い事、自宅での療養・カウンセリング通院などと両立しやすい
- 人間関係のトラブルを最小限に抑えられる
不登校経験が長引き、フルタイムでの通学に不安を抱える生徒には通信制高校が最適な場合があります。ただし、レポート提出や試験のスケジュール管理を自分でしなくてはいけないため、「自己管理能力」がある程度求められます。サポート校や家庭教師を併用することで、学習計画を立てやすくする方法もあります。
卒業率や就職率・進学率
「通信制高校だと卒業が難しいのでは?」という声も少なくありませんが、実際には以前に比べてサポートが充実しており、卒業率は年々向上しています。
大学進学実績も豊富な通信制高校や、就職サポートを行っている学校もあり、「通信制=学力が低い」というイメージは徐々に払拭されつつあります。

3.定時制高校
昼夜間部のメリット
定時制高校は夜間部のイメージが強いですが、中には昼夜間部を設置し、昼間に通える定時制を提供している学校もあります。夜間部の場合、夕方から夜にかけて通うため、昼間はアルバイトや家庭の手伝い、資格取得の勉強などに時間を使うことができます。
学年制と単位制
- 学年制
一般的な高校と同様に学年ごとに必要単位を履修し、年度ごとに進級の可否が決まります。留年があるため、ペースメーカーとしてはわかりやすいですが、留年を避けるためにある程度の出席日数や学習が求められます。 - 単位制
科目ごとに単位を修得していき、必要単位がそろった段階で卒業となるシステムです。学年による縛りが少ない分、自分のペースで学習を進めやすいという特徴があります。

4. サポート校やフリースクール連携
各種サポート内容
サポート校は、主に通信制高校と連携し、レポート指導や進学相談、メンタルサポートを行う民間の教育機関です。フリースクールは、不登校や学校に馴染めない生徒のために、少人数クラスや自由な学習スタイル、カウンセリングを提供しています。
中には「週2日はフリースクールで仲間と学び、週1日は通信制高校のスクーリングに参加する」といった形で柔軟に学習を進める生徒もいます。
学習面とカウンセリングの両立
サポート校やフリースクールでは、専門のカウンセラーや心理士が常駐していることが多く、学習だけでなくメンタル面のケアも重要視されています。特に長期の不登校を経験している生徒は、学業面だけでなく、自己肯定感や対人関係の不安が大きい場合があるため、こうしたサポートがある環境は非常に有用です。

高校進学に向けた具体的な準備とステップ
学校見学・オープンスクールの活用
不登校の状態だと「どこへ行っても結局うまくいかないのでは」とネガティブに考えてしまいがちですが、実際に校舎を見学し、先生や在校生と話すことで印象が大きく変わることがあります。
- 全日制高校
定期的に開催される体験入学や文化祭、説明会などに足を運ぶことで、学校の雰囲気や校則、部活動の様子などを知ることができます。 - 通信制・定時制高校
個別相談会やオープンキャンパスが行われる場合があります。具体的にどのようにレポートを提出するのか、スクーリングの頻度はどれくらいなのかなど、気になる点を直接聞いてみましょう。 - サポート校・フリースクール
個別の見学や体験参加が可能な施設もあります。少人数の学習スペースやアットホームな雰囲気が、自分に合うかどうかを実際に体感できると安心材料になります。

個別相談で必要となる書類やポイント
- 中学校の調査書(内申書)
不登校の期間があっても、近年ではその背景や理由をきちんと説明すると理解を示してくれる学校が増えています。特に通信制や定時制では、「今後、どのように学びたいか」を重視する傾向があります。 - 面接・作文でアピールできること
個別相談会やオープンキャンパスが行われる場合があります。具体的にどのようにレポートを提出するのか、スクーリングの頻度はどれくらいなのかなど、気になる点を直接聞いてみましょう。 - サポート校・フリースクール
・不登校の間に学んだことや得たスキル、興味を持った分野
・将来の目標や夢
・学校生活をどう変えていきたいか、どう挑戦したいか
など、前向きな姿勢をアピールすることが合否に大きく影響するケースがあります。

受験勉強の進め方(通信教育・オンライン学習など)
通信教育
Z会や進研ゼミ、学研など、中学生向けの通信教育サービスは多数存在します。
教材が定期的に送られてくる仕組みや、オンライン添削に対応しているところもあり、不登校でも学習ペースを作りやすいという利点があります。

オンライン学習サービス
スタディサプリ、YouTubeの学習チャンネルなど、映像授業をいつでも視聴できるため、理解が追いつかない部分を繰り返し確認するのに便利です。
スマホやタブレットだけで勉強できるため、場所を問わず学習を進めやすいのが特徴です。

学習計画の立て方
不登校期間が長い場合、学年相応の内容が抜け落ちていることも多々あります。特に英語や数学など、基礎的な単元でのつまずきを放置しないことが重要です。
最初は小学校レベルにさかのぼってやり直すことも視野に入れ、徐々にレベルを上げていくのが成功のポイントです。

家庭教師のアーチを利用するメリット
不登校の生徒が高校進学を目指すうえで、家庭教師サービスを利用する選択肢も大きな意味を持ちます。特に「家庭教師のアーチ」は不登校生徒の学習サポートに力を入れており、以下のようなメリットがあります。
1. 個別指導で学力不足を解消
不登校になった期間が長いと、教科ごとの理解度に大きなギャップが生じやすいです。家庭教師なら一人ひとりに合わせたカリキュラムを組み、必要なところから学び直すことができます。また、苦手科目だけ重点的に教えてもらうことも可能なので、効率よく弱点を克服できます。

2. 柔軟なスケジュール調整
塾や学校のように決まった時間に通うのが難しい場合でも、家庭教師なら自宅やオンラインで指導を受けられるため、体調やメンタルの状態に合わせて日程を変更しやすい利点があります。特に夜間や休日など、保護者の方が在宅している時間帯に合わせることも可能です。
3. メンタルサポートに注力
不登校の原因が学業だけとは限りません。人間関係や家庭環境、メンタル面での不安が大きい場合、指導者が生徒の気持ちに寄り添いながら進める必要があります。家庭教師のアーチは不登校生徒の指導実績が豊富で、単なる学習面だけでなくカウンセリング的なアプローチを大切にしているため、安心感を得られるでしょう。

4. 保護者への定期的なフィードバック
家庭教師は、生徒との一対一のやりとりだけでなく、保護者への学習状況の共有やアドバイスも行います。「今どんな単元でつまずいているのか」「どんな声かけが効果的なのか」など、保護者がサポートしやすい情報を得られることは大きなメリットです。
5. 進路相談・モチベーション維持
不登校の生徒は、勉強に対する意欲や自己肯定感が低くなりがちです。家庭教師が定期的に学習目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできるんだ」という感覚を取り戻しやすくなります。
進路選択におけるアドバイスも受けながら、目標設定を明確にしていくプロセスは、高校受験に向けて大きな力となるでしょう。

成功事例・体験談
不登校から高校進学に成功した人の声
Aさん(通信制高校へ進学)
- 背景
中学2年から不登校になったAさんは、友人関係のトラブルが原因で登校意欲を失ってしまいました。家にこもることが多く、学習はほとんど手つかずだったそうです。 - 転機
中学3年の夏、通信制高校のオープンスクールに参加した際、「自分のペースで通えること」「年間スクーリング日数が少ないこと」に魅力を感じ、検討し始めました。
さらに、家庭教師のアーチを利用して基礎学力の取り戻しをスタート。苦手だった英語と数学を一から学び直し、少しずつ自信をつけました。 - 結果
通信制高校の入試では、中学時代の出席日数の少なさを理由に厳しい質問があったものの、「自宅で勉強を続けていたこと」「オンライン学習に取り組んでいたこと」をアピールし、見事合格。
現在は週1回のスクーリングとレポート提出を着実にこなし、卒業後は専門学校への進学を目指しています。

Bさん(全日制高校へ進学)
- 背景
Bさんは中学1年の後半に体調不良から不登校になりました。学校に行きたい気持ちはあるものの、朝起きられず、親とのコミュニケーションもうまく取れない日々が続きました。 - 転機
担任の先生が紹介してくれた家庭教師のアーチを利用することで、まずは体調の良い時間帯に基礎学習を始めることに。家庭教師の先生がメンタル面にも配慮しながら学習の習慣をサポートし、少しずつ生活リズムを整えていきました。
中学3年生の夏には、全日制高校のオープンスクールに連れていってもらい、校内の雰囲気を知って「ここなら頑張れるかも」と思えたことが大きなモチベーションに。 - 結果
特色選抜を利用して受験し、面接では「体調不良からくる不登校」や「家庭教師との学習を通じて学力を回復させた過程」などを率直に伝えました。学校側も事情を理解してくれ、意欲を評価して合格。今は週5日通学をしており、最初は大変でしたが、家庭教師が引き続き週1回フォローしてくれるおかげで学習の遅れを取り戻せています。

親や周囲のサポートの重要性
不登校は、本人だけではなく保護者も精神的な苦痛や孤立感を抱えがちです。以下のようなサポートがあると、高校進学に向けて大きく前進できます。
- 保護者の協力
学校見学や説明会、家庭教師との面談に同席し、子どもの様子を客観的に見守ることで、本人も安心して取り組めます。 - 学校・スクールカウンセラーとの連携
中学校側の協力を得て、内申書に不登校の原因や現在の学習状況を正しく記載してもらうことも重要です。 - 家庭教師やフリースクール、NPOの活用
自分たちだけで解決できない場合、第三者の専門家や団体を上手に活用することが成功への近道です。

出席日数や学力不足をカバーするために
- 出席日数の扱い
不登校期間が長い場合、どうしても出席日数は少なくなります。しかし、先述のように出席日数だけではなく「今後の意欲」や「不登校期間にどのように過ごしたか」を評価する学校も増えています。面接や作文で正直に伝えることが大切です。 - 学力不足の対策
少しずつでも学習の習慣を取り戻すためには、通信教育やオンライン学習に加え、家庭教師などのマンツーマンサポートが有効です。基礎固めを丁寧に行い、無理のないスケジュールで学力を上げていきましょう。

【まとめ】不登校から
高校進学する上で
大切なポイント
1.多様な学習スタイルを知る
全日制だけにこだわらず、通信制や定時制、サポート校を含め幅広く情報収集しましょう。
学校見学やオープンスクール、オンライン説明会など、チャンスがあれば積極的に参加して自分に合った環境を探すことが大切です。
2.早めの情報収集と周囲の連携
不登校が長引くほど、情報不足や焦りが生じがちですが、早めに調べて動き出すことで選択肢は広がります。
保護者や担任、スクールカウンセラー、家庭教師のアーチなどの専門家とも相談しながら進めると安心です。
3.学習とメンタルの両面からアプローチ
不登校の背景には、学習面の遅れだけでなくメンタル面の悩みも深く関わっています。
学習面はオンラインや家庭教師を活用、メンタル面はスクールカウンセラーやカウンセリング機関を利用するなど、専門家の助けを得ることで無理なく前進できます。
4.家庭教師のアーチなどの個別指導を検討する
不登校生徒向けの指導経験が豊富な家庭教師を利用すれば、学習の習慣を取り戻しやすいだけでなく、自己肯定感を育てるサポートも受けられます。
受験対策をはじめ、学校選びや入学後のフォローまでトータルに相談できるのは大きなメリットです。
5.進学後も継続的なサポートを意識する
高校に合格してゴールではなく、入学後もきちんと通えるかどうか、学習とメンタルの両立が図れるかが大切です。サポート校やカウンセリングの利用、家庭教師の継続など、周囲の支えを得ながら焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。
【FAQ】よくある質問と回答

Q1. 不登校で内申点が低くても高校に行けますか?

A. はい、不登校期間があったとしても高校に進学する道は多数存在します。出席日数や内申点よりも、面接・作文・実技などを重視する学校も増えており、通信制・定時制であればさらに柔軟な評価基準を採用しているケースが多いです。
大切なのは「なぜ不登校になったか」「今後どう学びたいか」をしっかりアピールすること。家庭教師のアーチのようなサポートを併用しながら学力を確実に補うことも有効です。

Q2. 通信制高校の学費はどれくらいかかる?

A. 公立か私立かによって大きく異なります。公立の通信制高校であれば学費は比較的安価(年間数万円程度)ですが、私立の場合は施設維持費などが加算されるため数十万円以上かかることもあります。また、サポート校を併用する際には別途費用が必要です。
ただし、就学支援金制度や各種奨学金が利用できる場合もあるので、事前にしっかりと確認しましょう。

Q3. 定時制高校と通信制高校のどちらがいいのかわかりません。

A. それぞれメリット・デメリットがあり、どちらが向いているかは生活リズムや目標、性格などに左右されます。
・定時制: 夜間や昼夜間部があるため、アルバイトや別の活動と両立しやすい。対面授業が基本なので、教師やクラスメイトと交流しながら学びたい人に向いている。
・通信制: 自宅学習が中心で、自分のペースで進められる。登校日数も少ないため、体調面や家庭の事情がある場合にも学び続けやすい。
両方の学校説明会を比較してみると、より具体的な違いが見えてきます。

Q4. 家庭教師をつけるのはお金がかかるので不安です。費用対効果はありますか?

A. 確かに、家庭教師の費用は一見高額に感じるかもしれません。しかし、不登校で学習が止まっている期間が長い場合、個別最適化された指導が受けられるメリットは非常に大きいです。苦手分野だけを集中的に補うことができ、指導形態によってはオンラインも選択できるため、通塾の手間や交通費もかかりません。
また、学習面だけでなくモチベーション維持や進路相談、メンタルサポートまで行ってくれるサービスなら、結果的に時間と労力を大きく節約できる可能性があります。

Q5. 進学後にまた通えなくなったらどうすればいいのでしょうか?

A. 定時制や通信制高校には、転入や編入の仕組みが用意されている場合が多いです。たとえば、全日制に入学してみたものの体調面で通うのが難しくなったというケースでは、通信制や定時制に転校する選択肢もあります。
無理をして続けてしまうと、再び不登校になってしまうリスクがあるため、早めに学校や家庭教師、カウンセラーなどに相談して柔軟に対処しましょう。
まとめ
不登校という言葉の響きから、「もう高校には行けない」「将来の道が閉ざされた」と悲観的に考えてしまうかもしれません。しかし、実際には全日制・定時制・通信制高校、さらにはサポート校・フリースクールなど、学びの選択肢は多岐にわたります。自分に合ったペースや環境で学び直すことで、学力だけでなく自己肯定感を高め、将来の進路を切り開くことは十分に可能です。
特に、家庭教師のアーチのように不登校生徒へのサポート実績が豊富なサービスを利用すれば、「どこから手をつければいいのか分からない」「学校をどう選べばいいのか分からない」という悩みを一緒に整理し、具体的な学習プランを立てることができます。メンタル面のケアに力を入れながら、基礎から着実に学びを取り戻していくことで、高校進学はもちろん、その先の大学受験や就職、資格取得へとつながる道が見えてくるでしょう。
不登校の経験は、決して「失敗」ではありません。その過程で学んだことや感じたことも、将来の糧になる大切な経験です。何より、「進学をあきらめなくてもいい」という事実を知り、自分に合った方法で前に進んでいくことが大切です。
資料請求や学校見学、家庭教師の体験授業など、まずはできる一歩から始めてみましょう。あなたやあなたの大切なお子さんが、自分らしく学び、自分らしく未来を描くための一助になれれば幸いです。